
専門家コラム
column
中小食品製造業に多い労働集約型工場における生産性の尺度(人時生産性)について

中小企業が新しい事業を始める際にぜひ活用したほうが良いのが「補助金」や「助成金」。獲得するにあたって、それぞれの特徴を把握した上で戦略的に申請するほうが圧倒的に獲得がしやすくなります。
そこで本記事では、まず両者の違いや明確な定義、それぞれの特徴・取得難易度・申請時の注意点について解説します。
はじめに
中小企業における食品工場や飲食店に限らず生産向上の活動を行う際には、その改善活動の評価を行う数値化が必要になります。
「定義できないものは、管理できない。管理できないものは、測定できない。測定できないものは、改善できない」と日本の品質管理の祖であるウィリアム・エドワーズ・デミングがのべるように生産性の向上に関して定義→管理→測定→カイゼンとつながる一連を明確にすることが一歩となります。
今回は生産性の測定方法となりますマンレート(人時生産性)、マシンレートについてご紹介したいと思います。
生産性の評価方法
生産性を評価するためには商品を作る際の原価計算を行います。
原価計算には「固定費」「変動費」「損益分岐点」…
と、おなじみの言葉を見て読むのを止めないでくださいね。
ここではこれらを使用しません。その内容は別の専門家にお譲りします。
現場で生産性の評価&計算に使用するのは「直接費」と「間接費」です。
私の食品業界の経験で現場の管理者が「変動費率が~」や「限界利益が~」なんて計算して話している人と出会ったことがない(大手企業は別かもしれません)です。加えて作業者レベルが、理解できる生産性の定義&測定でなければ、カイゼン活動の継続が難しくなります。
いくら生産工学や原価低減の先生が現場担当者に講習しても使えなければ意味のないものになってしまいます。
そこで、いろいろな生産性に対する評価の方法が有りますが、ここでは作業担当者が実際に使える評価方法を紹介します。
なぜ食品製造業では「直接費」「間接費」で生産性を評価するのか
「直接費」「間接費」は文字通り、製品を製造するに当たり、明確な数量が特定できるものとそうでないものでわけます。
直接費:原料、資材費、直接作業員の作業時間(または製造装置の稼働時間)
間接費:電気、ガス、水道など、間接部門の人件費、利益(直接費以外のもの)など
加えて人手主体の労働集約型工場か、機械生産中心の工場かで使い分けられる生産性の尺度として二つを挙げます。
マンレート(賃率・人時生産性)→労働集約型:小規模・安価&汎用機・8-17時操業
マシンレート→装置生産型:大規模・高価&高速専用機・早朝→深夜(24時間)稼働
なぜ食品製造業でこの指標を使うかというと、
食品製造業(飲食店)は工業製品と比較して
A:小ロット多品種生産
B:工程が多数あり各工程に専用装置がある
C:加工工程に複数の製品、作業員が混流している。
D:水・電気・蒸気・化石燃料・エアーを各商品に按分計算が難しい
E:原料→加工→出荷までに数日またぐケースも混在する。
などがあり、1アイテムに製造コストがどの位かかっているか計算しづらく、生産資源が商品ごとにどのくらい掛かっているかを求める事が難しいためです。
そのため生産資源(ここでは人または物)が活動する単位時間当たりに製造コスト(場合によっては利益も)を乗せ按分して計算します。
マンレート=(直接作業者の労務費+すべての間接費)÷直接作業員の総労働時間
人が少ない時間で多くのものを生産すると生産性が高いと評価できる。
マシンレート=(直接作業者の労務費+すべての間接費)÷ライン(装置)の稼働時間
ラインや装置が長時間&高速稼働し大量に作った方が、生産性が高いと評価されます。
同一の工場でも労働集約型の工程、ラインはマンレートで計算し、装置生産メインの工程はマシンレートを使い分けるケースも有ります。
多くの中小食品製造業では多くは労働集約型の工場かと思います。そのような工場では作業員は機械と異なり多種多様な仕事のできる重要な生産リソースです。勤務時間に作業する人がどれだけ付加価値を付与する作業ができるかが高い生産性であると言うことができます。
また、マンレート、マシンレートの考え方は計算しやすい上に難しい生産性の計算で求められた生産性と大きく乖離しない事が多いというメリットが有ります。

マンレート、マシンレートの生産性評価基準としての注意点
「間接費」「直接費」によって生産性を評価するときの注意するところは、自社の工場が装置生産型か労働集約型か把握し、マンレート、マシンレートを使い分けることです。
装置生産型の工場でマンレートの評価を使用すると少ない人数で高い生産量を得ることができますが、装置の稼働率が落ち、装置の減価償却、メンテナンス費の方がずっと高いため工場全体の生産性は低くなってしまいます。
一方で労働集約型にマシンレートを適応すると「工場で速く・たくさん作った方が、生産性が高い」と評価され、トヨタ生産方式における7つのムダの「作り過ぎのムダ」「在庫のムダ」「加工そのもの(作業そのもの)のムダ」が発生する原因となります。
残念なことに、労働集約型工場にマシンレートの考えを持込んで考えている生産管理者は多いです。1日当たりの製造量が多い=工場の生産性が高いと考えている人です。
多くの労働者を使って、機械をフル回転させて時間当たりの製造量を追い求めるケースです。
例えば…
マシンレートで生産性を評価している工場では
先月は製品70個/日を作る。
今月は製品100個/日を作る。
このケースでは今月の方が、生産性が高いと評価されます。
マンレートの工場では
先月は5人で製品70個/日を作る。
今月は10人で製品100個/日を作る。
先月→14個/人 今月→10個/人
で、製造数は増えても今月の方が、生産性が低いと評価されます。

労働集約型の生産性の評価法(人時生産性)の実例
記事の容量にも限りが有りますし、マシンレートに関しては他の産業でも使用されているので、ここでは割愛させて頂きます。
食品製造業に多い労働集約型の工場における生産性の評価方法について実際の運用例について述べます。
カイゼンするには生産性の定義、管理、測定が必要です。生産性の評価の場合は管理よりも先に測定がくる場合が多いですので、定義→計測→管理→カイゼンとして例を挙げます。
定義:生産性=製造個数(または金額など)÷(直接作業者の人数×時間)
測定:100個の製品を3人で8時間かけて製造した。
製品100個÷(3人×8時間)=4.17個/人・時間
管理:今日3.0個/人・時間 標準4.0個/人・時間
今日は生産性が標準より低い何かトラブルが有ったのか?
一方で
今日5.0個/人・時間 標準4.0個/人・時間
生産性が標準より高い。必要な加工時間が不足しているのではないか?
ばらつきを把握し、標準近いものになるように対応するのが管理となります。
カイゼン:作業の標準を変えてテストを行った。生産性(個/人・時)が向上した。
品質も維持できるのでこれを新しい標準とする。
とても簡単ですがこの様に、生産性を評価&カイゼンしていきます。生産量と作業者×作業時間だけの測定ですので現場担当者も生産性の尺度が判り易いものになります。
マンレート(人時生産性)を尺度とした改善の注意点
マンレートを生産性の尺度とした時に、注意点があります。労働強化にならないようにするという事です。
決まった時間の間に沢山作るという事になると、管理者がムチを使って「早く動け」「休むな」「ムリをしろ」とムダを排除せずムリをさせますと短期的にはわずかに生産性は向上しますが、長期疲労により休みが増える、労災が増える、不良品の量が増える、採用しても人が定着しないという事が起き、トータルで生産性は向上しませんし、デメリットに対応するための間接部門のコストが跳ね上がります。
そこで、ムリ・ムダ・ムラを排除することで生産性を向上させていくのです。カイゼンは労働強化では有りません。むしろムリを排除しますので相反するもので有ります。
マンレートで製造原価、製造見積を算出する
食品製造業は先に述べた様に多くの工程や加工機械、冷凍冷蔵保管庫など、機械、電子製造業と比較して安価で単機能装置を使用することが多く、どれにどのくらいのコストが掛かったかを算出するのは非常に難しいです。
そこで、間接費を総労働時間に按分して製造原価を求めます。
仮定条件
直接作業員が10人で労務費500万円/人→総労務費5000万円
総労働時間2,000時間/年×10人=20,000時間
間接部門の労務費、減価償却費、光熱費、その他製造に掛るすべての支出=2200万円
マンレート=(5000万円+2200万円)÷20,000時間=3600円/時間
=1円/秒
あるグラタンを作る原料、容器、袋、箱の直接費を100円/個として、製造の直接作業時間が1分/個だったとすると
100円/個+(1円/秒×60秒/個)=160円/個
このグラタンの製造原価は160円となります。生産性の向上により直接作業が10秒減れば、製造コストが150円となり10円/個のコストダウンとなります。
マンレートは昨今のエネルギー価格の高騰、賃上げにより上昇する傾向があるので年または月で再計算しマンレートを求めます。現場作業員はマンレートを直接加工作業時間でかければ製造原価を簡単に求める事ができます。
マシンレートは同様に、製造装置の稼働時間に按分して計算していきます。
マシンレートでは直接作業者の労務費を直接費とするか間接費とするかは各社の判断に分かれます。食品製造業ではそこまで高価な装置はそう多くは無いと思いますので、ここでは直接作業員の労務費を直接費として計算します。
製造原価=原料費+直接作業員の時給+(装置の稼働時間×マシンレート)となります。
おわりに
中小規模の食品製造業では労働集約型の企業が多いのでは、と思います。そのようなタイプの製造業は人時生産性、マンレートに注目して生産性を評価することが特に重要です。マシンレートを適用してしまうと大量に作ることが「生産性が高い」と評価してしまい、市場の需要に合わない過剰な生産で不良在庫となりコストが高くなる恐れが有ります。
また、カイゼンは労働強化では有りません。ムリ・ムラ・ムダを削減することで生産性を向上させていきましょう。
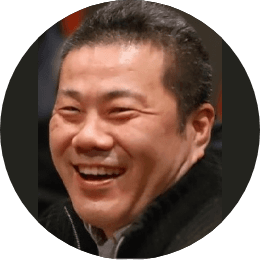
この記事を書いた人
山本 宗幸20年にわたり中規模食品会社で商品開発、事業開発、製造技術、生産性向上の業務を行ってきました。「技術で食と人を豊かにしたい」をミッションに活動しています。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


