
専門家コラム
column
東南アジア「昆虫食開拓」から学ぶ、新規市場開拓の極意

「どうしたら海外で新しいマーケットを開拓できるか?」
「不確実なマーケットに進出するべきか、意思決定が難しい」
このような疑問はありませんか?
既存マーケットに進出する場合、すでにユーザーの需要が明らかとなっているため、先駆者となるプレーヤーの勝ち筋を参考にしつつ、既存プレーヤーとの差別化により、市場獲得を目指していくことができます。
一方、需要があるかどうかさえわからないような、新規市場を開拓していく場合、成功するかどうか不確実ですし、参考にできるプレーヤーがいないため、自社で試行錯誤して道を切り拓いていく必要があります。例えば東南アジアで、昆虫食市場を開拓しているプレーヤーなどはその一例です。
このように、新規市場を開拓していくためには、何が重要なのでしょうか。
本記事では、ベトナムでの事業歴10年・日本企業の海外進出支援事業を営む筆者が、東南アジアの昆虫食最新事情について解説していきながら、そこから見えてきた新規市場開拓の極意をお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。
1.昆虫食が一般的である東南アジア
東南アジアには、昆虫食文化が存在します。
タイ・ミャンマー・ラオス・カンボジアなどでは、昆虫を食べることが一般的です。
例えばカンボジアでも、店頭・屋台で販売されているだけでなく、食卓にも昆虫食が出てきます。日常的に食べられており、身近な存在なのです。
そんな東南アジアでは、「健康的な食材」として、昆虫食が現地向けに販売されています。
また、昆虫食養殖工場も存在し、現地で昆虫食を生産し、アメリカやEU向けに販売するプレーヤーも複数存在します。
日本向けには、食用としての価値は現時点で受け入れられていないため、昆虫を活用したペットフードから市場開拓が始まっています。
2.昆虫食の特徴

昆虫食は、
✔️健康効果がある
✔️工夫次第で生産コストが抑えられる
✔️環境にも優しい
などの特徴があります。
2-1 健康効果がある
昆虫食の代表的な存在である「コオロギ」の場合、タンパク質が豊富で、鉄分・亜鉛・他の栄養素もあり、栄養価が高いです。
また、ペット向けの昆虫食であれば、便通を抑えられたり、皮膚のカイカイ(犬がしきりに体を掻く症状)を抑えられるなど、健康効果もあります。
このように、人に対しても、ペットに対しても健康効果が高いのです。
2-2. 出荷期間が短く、工夫次第で生産コストが抑えられる

例えばコオロギであれば、卵の状態から45日間でコオロギが成長し、出荷できます。
生産自体も場所を取らないため、家のデッドスペースで生産できますし、コオロギ自体小さいため、限られたスペースでも大量生産が可能です。
コオロギの成長には、30度ぐらいが適温であるため、日本だと冬の電気代が高くなってしまいますが、常夏の東南アジアでは電気代もかかりません。
このように、昆虫食は工夫次第で生産コストが抑えられる業態なのです。
2-3 環境に優しい
昆虫食が、環境負荷が大きい豚肉・牛肉に置き換わるだけでも、環境にプラスの影響があります。
それだけでなく、昆虫の餌にフードロスを活用することができるため、ゴミ削減にもつながるなど、昆虫食は環境に優しいものなのです。
3.昆虫食のターゲット・提供価値
このような特徴がある昆虫食を、具体的にどのようなターゲットに向けて展開してビジネスにできるのでしょうか。
コオロギを乾燥化させて粉末化したコオロギパウダーを、カンボジアで生産・展開している、株式会社エコロギーの皆様に話を聞きました。
すると、「健康に食材を食べたい、ペットや子供に健康的な食事を食べさせたい」というニーズに応える食材としてミドルアッパーの富裕層をターゲットに展開を予定しているようです。
例えばカンボジアでは、お金を持ち始めた中間所得者層の母親がターゲット。彼らの「子供にヘルシーなお菓子を食べさせたい」というニーズに応える食材として打ち出していくとのこと。
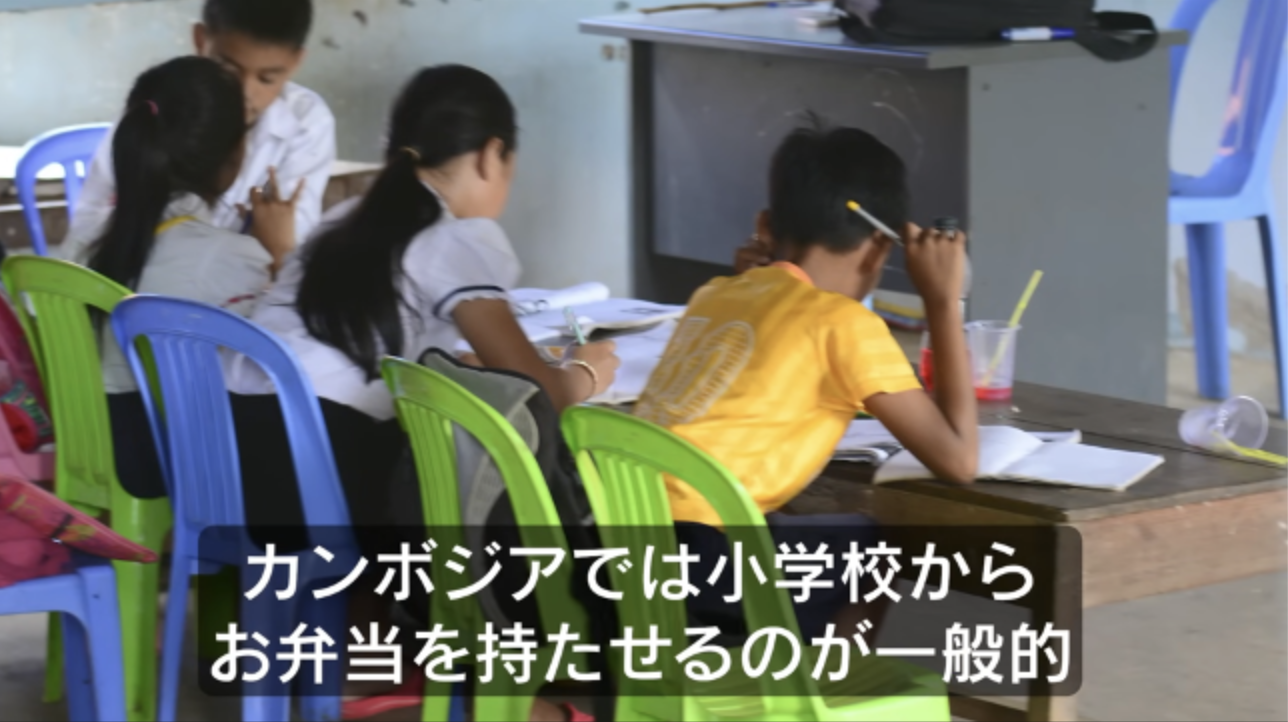
実際に現地の子供たちの食事事情を深堀していくと、カンボジアでは小学校からお弁当で、お弁当と一緒に持っていくお菓子が「安くて健康に悪い」ことが気になっている親が存在するため、そこを代替する食材として打ち出せなか模索されているとのことです。
カンボジア以外の、マレーシアではハラルの問題があるため、ヘルシーなペットフードとして打ち出し、ベトナムでは忙しいOL、ミドルアッパーの富裕層たちの「健康的なスナックが食べたい」というニーズに応える食材として、現時点では需要があると見立てられているのです。
4.昆虫食市場開拓から学ぶ!新しい市場を開拓するために重要なこと
昆虫食が一般的な東南アジアとはいえ、昆虫のパウダーを活用したスナック・食材は完全に新しい市場です。
そのような不確実性の高い、新しいマーケットを開拓していくために重要なのは、「PDCAを回す」ことです。
当たり前のことではありますが、この当たり前のことを行うことが難しく、多くの企業ができないため、重要性を改めてお伝えします。
4-1 実証実験しながら、生産方法のPDCAを回す
生産方法自体も確立されていない場合は、生産方法自体もPDCAを回すことが必要です。
✔️どのような生産方法だと、品質を高められるか
✔️どのような生産方法だと、コストを抑えられるか
などの観点でPDCAを回していきます。
実際に、株式会社エコロギーの方に話を聞くと、提携しているカンボジアの昆虫食農家の方と一緒に実証実験をやりながら、「どのような餌がいいか」「どのような環境がいいか」を検証し、常に改善しながら進めていらっしゃいます。
4-2 試験販売しながら、マーケティング・ブランディングのPDCAを回す
また、営業販売や、マーケティング、商品のブランディングについてもPDCAを回すことが重要です。
店頭で試験販売・テストマーケティングを実施することで、
✔️ユーザーが食品を「美味しい」と感じてもらえるか
✔️ユーザーが食品の味について、どのような感想を抱くか
✔️ユーザーが実際に食材を買うかどうか
✔️ユーザーが実際に食材を買う場合、どのようなことに価値を感じて、買うのか
✔️複数の商品を試験販売する場合、売れる食材と売れない食材の違いは何か
などが浮き彫りになってきます。
試験販売によって、売れれば、投資効果を見込むことができるので、海外進出の意思決定のきっかけになります。
しかしながら、試験販売において一番の収穫は、「売れない時」です。
それによって、「何が課題で、何を改善すれば売れる可能性が拓かれるのか」について、重要な示唆が得られるからです。
試験販売・テストマーケティングを活用しながら、営業・マーケティング・商品ブランディングについてもPDCAを回していきましょう。
5.まとめ
本記事では、東南アジアにおける昆虫食の最新事情をご紹介しながら、新規マーケット開拓の極意をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか?
詳しくは、こちらのYoutube動画で、昆虫食の事例を詳しくお伝えしているので、ご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=dtxlxfRejlE
https://www.youtube.com/watch?v=pFNMxmAX3Nw
ぜひ本記事やYoutubeをご確認いただきながら、海外進出のディスカッションをしていただければと思います。

この記事を書いた人
荒島 由也スター・コンサルティング・ジャパン代表、STAR KITCHEN創業者。ベトナムで料理教室、洋菓子製造・販売事業も展開。ホーチミン高島屋に店舗を持つ他、 スターバックス、セブンイレブンなどを取引先に持つ。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


