
専門家コラム
column
中小・小規模食品メーカー様向け 百貨店との取引を目指す戦略 その③

III.百貨店との取引を実現させる方法
さて、いよいよ本題です。これまで百貨店との取引について滔々と述べてきましたが、いざ実際に百貨店と取引するにはどうすれば良いのか。取引したいと思ってもその方法がわからない、なんていう事業者様も多いのではないでしょうか。
正直に申しあげて、こちらから百貨店と取引したい意向を百貨店側に伝えてもなかなか取引には至らないパターンがほとんどです。ましてや食品フロアにテナント出店なんてなかなかできません。ではどうすれば良いのか、以下にその手段を示します。
①短期間催事への出店
②既に百貨店と取引している事業者からの紹介
③SNSなどで自社製品が消費者に支持されている様子をUPさせていくことで、百貨店側からの声かけを待つ④外商部とのネットワークをつくる
⑤直接訪問
⑥ネット上で取引先を募集している店を探す
⑦商工会議所やその他行政の支援機関での展示会、ビジネスマッチングフェアに出展
①短期間催事への出店
百貨店ではよく“○○フェア”が開催されていることをご存じでしょうか。その多くは催事場が上のフロアにあり、北海道フェアであったり、九州フェアであったり、定期的に趣味趣向をこらしたイベントを実施しています。ここに出店されるお店は、企画会社が募集していたり、百貨店側が直接誘致していたりします。もし御社にその気があれば、百貨店に直接電話して催事への参加方法などを問い合わせても良いですし、企画会社が間に入っている場合だとその企画会社について教えてもらっても良いです。手っ取り早いのは、百貨店の短期出店をしたことがある事業者からその百貨店の担当者の連絡先を教えてもらうことです。御社の商品に魅力があり、その催事の趣旨に合うものであり、集客も見込めそうだと判断されれば取引が実現する可能性が高まります。もしダメでも何がダメなポイントだったのかを相手から聞き出すことを忘れないでください。今後の出店交渉に活かすポイントを掴むのです。
そして短期間催事への出店が叶ったとしても、どれだけの集客力があってどれだけの商品を用意していかなければならないのか、事前にある程度は把握しましょう。百貨店側からすれば、せっかく短期間で催事を行い、1人でも多く集客して1円でも多く売り上げたいのが本音。参加してくれる事業者には売り切れてチャンスロスにならないようにたっぷりと商品を用意してもらいたいのです。しかしだからといって山ほど商品を準備しても、仮に雨が続いて集客が予定より少なければ売れ残った商品は全て御社の負担となります。非常に難しい判断ですが、そこはしっかりと予測をたてましょう。
②既に百貨店と取引をしている事業者からの紹介
“信用”を重視する百貨店では、既に取引のある事業者からの紹介は最も安心できるものといえるかも知れません。百貨店側でも常に新しい取引先の開拓は念頭にあるのですが、手当たり次第に開拓するわけにはいかず、こういった既存取引先からの紹介は非常にありがたいものなのです。
食品メーカーにおいては、既に百貨店と取引のある事業者とのネットワークを活用して百貨店担当者との交渉に入るわけですが、この交渉において紹介いただいた事業者の顔をつぶさないように心がけましょう。あくまでもスマートな対応を心がけて、仮に取引が成立しなかった場合でも“さすがは○○さんから紹介してもらった事業者さんだ”といってもらえるように振舞えば、また別のお話しがやってくるかもしれません。“今回はご縁がなかったですが、今後○○百貨店の盛り上げにお役に立てることがありましたら何でもおっしゃってください。協力させていただきます。”この一言で百貨店側担当者は確実に御社のことはインプットされます。
③SNSなどで自社製品が消費者に支持されている様子をUPさせていくことで、百貨店側からの声かけを待つ
これは多くの事業者が取組んでいることかもしれませんが、ひとつポイントがあります。多くの事業者様は、自社の商品をキレイに撮ったり、美味しそうに撮ったりすることで満足していませんか?もちろん商品をキレイに見せること、美味しそうに見せることは大事なことです。むしろこの逆であれば消費者は興味をなくすかもしれません。
ここでいうポイントとは、あくまでも百貨店側担当者にササる魅せ方です。つまり百貨店側担当者は何に反応するかというと、“行列ができているのかどうか”なのです。他の百貨店ではまだ販売されてなくて、しかし街中に埋もれている行列のできるお店の商品であれば、百貨店は興味を示します。むしろ実際の商品がキレイかどうか、美味しそうかどうかよりも、“行列ができているのかどうか”の方に興味が湧くものです。
もし御社が店舗を構えているのでしたら、その店舗に行列ができている様子をSNSにアップさせてください。店舗を構えていないのでしたら、納品先に行列ができている様子をSNSにアップさせてください。百貨店側の目に留まれば、興味を引く可能性が高まります。
私の支援先事業者の一つでは、自身は全く百貨店に営業せずに、インスタグラムを見た百貨店側からの声かけだけで、いくつもの百貨店に出店しています。
④外商部とのネットワークをつくる
皆さん、外商部って聞いたことありますか?百貨店には百貨店の上お得意様のみを対象にしている部署があります。百貨店によって差はありますが、年間〇百万円~〇千万円程度のお買い上げをいただく顧客を外商顧客として百貨店各社は囲い込んでいるのです。私自身が某百貨店の外商部の外商員をやっておりました。そこでは通常の庶民の生活からはかけ離れたお買い物をされる消費者が当たり前のように存在しています。2キャラットのダイヤモンド、有名作家の掛け軸、スイスの有名ブランドの宝飾時計、ペルシャ絨毯、呉服など、ありとあらゆる高額商品を売ってきました。
このように高額商品を取り扱う部署ですが、実は“企画品”として事業者からの持ち込み案件で食品の数千円~数万円の食品が毎月毎月取り扱われています。百貨店によって差はありますが、何かしらの“企画品”が外商部に持ち込まれ、売上確保のために外商員が自分の顧客に電話をかけてかけて注文をいただきます。たとえ数千円~数万円でも外商員ひとりひとりが件数を重ねれば大きな売上となるのです。私がいた外商部では毎月毎月、外回りから帰ってきてから何軒も電話して注文をいただいていました。
前置きが長くなりましたが、この外商部とネットワークを構築できれば、“企画品”として採用される可能性も高まり、さらに食品売場に繋いでいただけることもあるのです。では、この外商部とのネットワークはどのようにして構築していくのかについてお話しします。
1つは既に外商部と取引のある事業者の方に紹介いただく方法、もう一つは外商部と取引のある顧客に外商員を紹介してもらう方法、そして3つ目は自社で中元や歳暮などを注文する際やゴルフコンペの景品の注文などで高額な注文になる場合に、外商サロン(外商部がある百貨店では大体設置されています)にて外商員を紹介してもらう方法です。この3つ目の方法は外商員と繋がる方法としては効率が良いかもしれません。まず先に目当ての百貨店の外商顧客になってしまうことから始めるわけです。ただ、それほど買物が続かない場合や業績が奮っていない場合は取引自体を遠慮されてしまうかもしれませんが・・。
⑤直接訪問
これはなかなか成功率は低くなりますが、白か黒かがはっきりわかる点で試してみる価値はあります。担当者の所在によりタイミングが重要になりますが、タイミングさえ合えば話を聞いてくれる可能性はあります。そして話を聞いてくれさえすれば、自社の商品やサービスの魅力に対してどう思われたのか、評価はどうなのかを直接聞くことができて有益な情報となります。
⑥ネット上で取引先を募集している店を探す
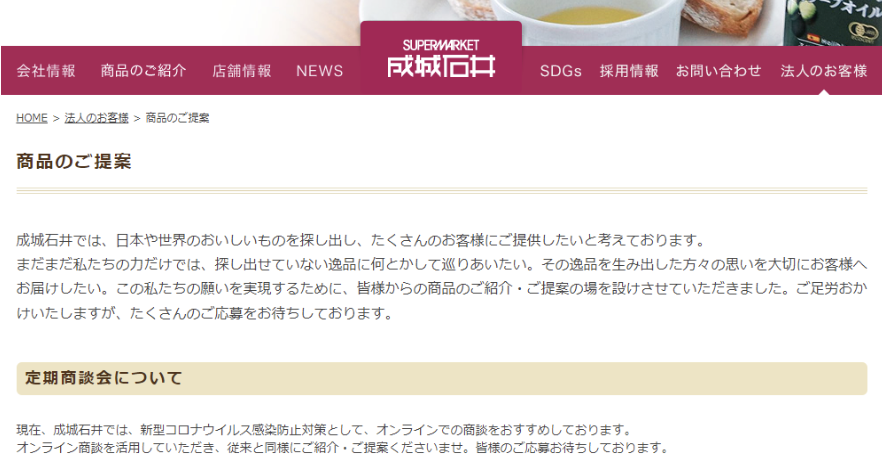
上の画像は成城石井さんのHP(商品のご提案法人のお客様スーパーマーケット成城石井)より引用したものですが、各小売店では他店との差別化を図るために、常に魅力的な商品をもつ取引先を探しています。成城石井さんのように、ネット上でその内容をお知らせしていただいていれば、非常に申し込みしやすいですよね。
⑦商工会議所やその他行政の支援機関での展示会、ビジネスマッチングフェアに出展
この方法はかなり実現性の高い方法と言えます。各食品メーカーさんの地元の商工会や商工会議所、中小機構(中小企業基盤整備機構)など、事業者の支援を担っている機関が主催するビジネスマッチングイベントに参加することで、百貨店バイヤーとの接点をつくることができます。ただ、それほど多くの数が開催されるわけではなく、1年のうちで時期が決まっています。それぞれの地元の機関に問い合わせてみてください。
以上、百貨店と取引を実現する方法について述べてきましたが、日頃から常に百貨店との取引を目指す旨を発信してネットワークを拡げていけば必ず実現する日がやってきます。申しあげたとおり、百貨店との取引はそれほど儲かるものではないかもしれませんが、それ以上のメリットが存在することも確かです。是非、チャレンジしてみてください。

この記事を書いた人
竹内 涼太百貨店外商を約8年、食品SM共同経営約16年、食品SM内でのテナントとして青果・日配・米等扱う商売を約16年経験してきました。「売る」ためのあらゆる手段を駆使して事業者様を応援します!
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


