
専門家コラム
column
社内の労働環境やマインドが生産性に与える影響について

はじめに
生産性の向上にはムダを排除する方法が主な手法かと思います。またムリ、ムラを排除することも直接、間接的に生産性を向上できます。いわゆる「ムリ、ムダ、ムダ」と呼ばれる3Mを削減し生産性を向上させます。
特に製造業ではトヨタ生産方式における7つのムダが有名です。
「加工の(作業そのものの)ムダ」
「在庫のムダ」
「作りすぎのムダ」
「手待ちのムダ」
「動作のムダ」
「運搬のムダ」
「不良を作るムダ」
が挙げられています。
(飾って豆腐と覚えます。)
これらのムダのほかにも人間の考え方、心理から生まれるムダも有ります。今回はこのムダに関して深堀していきたいと思います。
心理からくるムダ
皆さんは心がネガティブな状態になっているとき、例えば怒っている、悲しんでいる、落ち込んでいる、恐怖を感じているとき仕事の速度、正確性が落ちてしまう事を経験的にご存じかと思います。
特に近年ではパソコンソフト、アプリの機能の向上や製造現場では高性能の機械やロボットなど正確性を求められる作業、繰り返し作業の多くは自動化されており、定型業務から非定型業務へと増えてきています。特にクリエイティブ系やサービス系などの非定型業務は心理的な状態が品質に大きく左右されることは皆さん経験済みで根拠を上げるまでもないかと思います。
トヨタ生産方式の7つのムダの中には心理面にアプローチしたものが有りませんが、近年そちらにも注目が集まっていますのでご紹介したいと思います。

トヨタ生産方式の「8つ目ムダ」
トヨタ生産方式に関する情報を深く調べた人には「8つ目のムダ」を目にした事がある人がおられると思います。トヨタ生産方式の8つ目のムダは「ムダをムダと思わないムダ」、もしくは「何もしないムダ」と呼ばれています。(ほかにも有りますが主なものを記載しています)
ムダのある工程を見てムダが有ることは認識しているが
「前やったがダメだった」
「時間がなくてそれどころではない」
更に悪いものになると
「前から、このやり方で製造してきている最高形であり、カイゼンできる所は存在しない」
と考えカイゼンをおこななおうとしない、そもそもムダだと気付いていないからカイゼンのしようもない状態のことを指しています。
私の恩師で、食品製造業×トヨタ生産方式による生産性向上の指導をされていた小杉直輝先生は8番目のムダの事を「目の鱗」と呼んでいました。
小杉先生が若い時に名古屋工業大学の熊谷先生から指導を受けられた際に熊谷先生がおっしゃられた言葉だそうです。
「普段は現場のムダが見えない。これは目に鱗がついているからで、鱗を剥がせばすぐにでもムダが見えてくる」
「落ちた鱗はすぐ生えてくる。生えた鱗を落とす努力をするとともに、二度と鱗が生えないように訓練する事が大切だ」
小杉先生も熊谷先生から指導を受けた当初は、ピンと来ていなかったそうです。ある日、熊谷先生の指導を録音していたテープを聞き返していたところ、一つの気づきから連鎖的にムダが見えるようになり目の鱗が落ちた瞬間を鮮明に覚えておられるそうです。
そして「現在が最高型だ」と思いこまないように…「目から鱗が生えないように」意識され続けたそうです。
製品を製造するにはやむを得ず、ムダな作業をしなければならないことがあります。これを、「正味作業を成立させるためのムダな作業を仕方なくおこなっている」と解釈するか「これは必要な作業だ」ととらえるかでカイゼンのヒントが見える・見えない、の差が出てきます。
リーン方式での「8番目のムダ」
皆さんは「リーン方式」という言葉をご存じでしょうか?リーンとは「贅肉が取れた」という意味です。トヨタ生産方式をベースに1990年前後にマサチューセッツ工科大学ジェームズ・P・ウォマック氏らにより研究・体系化された生産方式です。世界的にはリーン方式の方が、認知度が高いとされています。
この理論ではトヨタ生産方式において、ボトムアップ型のカイゼンが多く、部分最適になりがちなるという弱点を指摘しています。トヨタ生産方式はムダ取りが得意ですが、3M(ムリ・ムダ・ムラ)の中のムラから発生するムダも少なくありません。
リーン方式では、このムラなどから発生するムダを削減するために全体最適を目指してカイゼンをおこないます。そのためにはトップダウン型のカイゼンを行い組織のバランスを調整し生産性を向上させるのが特徴です。
このリーン方式は2000年代に入ると日本に紹介され、製造の現場だけでなく間接部門、販売部門にもスポットが当たっている点も強みであり、現在の日本に逆輸入された形となっています。
そのリーン方式で8番目のムダとして出てくるのが「ニーズのミスマッチのムダ」です。リーン方式は市場の「ニーズ」を重要視しています。例えば製造している商品が、目まぐるしく変化する市場のニーズと一致していないと在庫になったり、市場ニーズより過剰な機能を付与したために高額な売価となり販売力が低下してしまいます。
また、会社の中でもニーズのミスマッチが発生します。生産部門は簡単で切替の少ない製品を作りたいニーズ、販売部門は安いものを沢山売りたいニーズ、経営者は利益の高い製品を売りたいニーズが有り、これが必ずしも市場のニーズと一致しないということが起こります。
各部門のニーズが全て悪いというわけではなくバランスが大切です。市場のニーズに一致させるべくトップダウンにより各部門の行き過ぎたニーズを管理して会社の全体最適を目指していきます。
心に由来するムダ
先に上げたように心理状態や人間関係の良し悪しは生産性・正確性を大きく左右します。その実際の例をご紹介します。
◆ホーソンの実験
1920〜30年代におこなわれた実験です。米国のウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場でおこなわれ、こう呼ばれています。
実験では「作業の生産性が環境や労働条件で向上しないか?」という目的の元、照明の強さを変えたり、休憩時間、軽食、温度、湿度、チーム編成などいろいろな条件をテストしました。
また、延べ2万人と面談しました。
この中で環境による差はあったものの、人間関係の方が大きく左右されることが判りました。
これとは別に「注目されることで成果を上げようとする内的動機」が強まり生産性が向上したことが確認されホーソン効果と呼ばれています。
無礼な人、叱責に関する心と作業への影響
他人から無礼な態度、不快な言葉遣い、叱責を受けた人だけでなく、それを見たり、聞いていたりする人も生産性を低下させることがわかっています。
『Think CIVITY 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』 クリスティーン・ポラス著(東洋経済新報社)において、著者が米国における振る舞いと心理に関連するデータについてまとめており、引用します。
アメリカ心理学会によると米国では職場のストレスにより5000億ドル/年の損失。5500億日/年の就業日が失われ、職場で発生する事故の60〜80%、通院の80%が職場のストレスに関係しているとされます。
17業界800人の管理職、従業員における「職場で誰かから無礼な態度をとられている人」に対する調査では
48%の人が仕事にかける労力を意図的に減らしている。
47%の人が仕事にかける時間を意図的に減らしている。
38%の人が仕事の質を意図的に下げている。
80%の人が無礼な態度に気を病み、時間を奪われている。
63%の人が無礼な人を避けるために仕事の時間が奪われている。
25%の人が無礼な人のストレスのせいで顧客対応が悪くなることがある。
と答えています。
大学生を対象にした実験で、見ず知らずの人に叱責された場合
アナグラム(文字を入れ替えて別の単語を作る)テストが61%低下
ブレインストーミング(日用品を別の使い方を提案する)テストで50%低下
一方で、叱責された人がいる場面に立ち会った場合は
アナグラムテストが20%低下
ブレインストーミングで30%低下
このように、直接的に心のダメージを受けただけで無く、叱責された人を見ただけでも認知能力が低下します。
無礼な態度を連想させる言葉を使って文章を作る作業を行っただけでも
記憶できる文字の数が17%低下
数学の問題の回答でのミスが43%増加
言葉の順番を思い出すテストで86%低下
以上から職場の人間関係の良し悪しは人間の生産性や正確性に大きな影響を及ぼすことが示唆されています。

おわりに
いかがだったでしょうか?近年ではルーチンワークが機械化、自動化され非定型業務が増えている中で人間の考え方や心理状態が生産性に及ぼす影響は無視できないものと感じて頂けたら幸いです。私が低い生産性でお困りの方には「すぐに生産性が向上する魔法の杖はパワハラやいじめを排除する事です」とお伝えしています。
機械化やIT化、3Mの削減は生産性の向上の手段ですが人の心も生産性を大きく左右しますので軽く考えずに対応する事も重要になります。
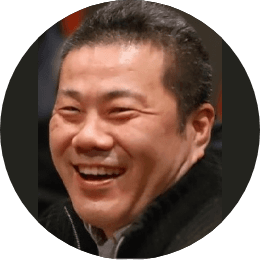
この記事を書いた人
山本 宗幸20年にわたり中規模食品会社で商品開発、事業開発、製造技術、生産性向上の業務を行ってきました。「技術で食と人を豊かにしたい」をミッションに活動しています。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


