
専門家コラム
column
生産性改善を始めるときの現場の本音とその対応&準備

食品工場に限らず製造業は原料高騰や人手不足などの多くの課題を抱えており、会社の中で生産性向上のためのカイゼン活動(改善ではなく世界基準のKAIZENとしてカタカナで記載します)に取り組もうとしている企業が多いと思います。
これまでに組織立ってカイゼン活動を実行したことがないという所は稀かと思います。その一方でなかなか、うまく機能していないと悩んでおられる方も多いかと思います。
実際にカイゼン活動をおこなうのは現場の担当者であり、その本音を掴み適切な対応や準備をすることで持続的な活動にすることが容易になります。
現場と経営者の本音
経営者がある日、社員を集めてカイゼン活動を始めるべく、スピーチをおこないました。
その時の現場作業員はどのように考えているでしょうか?
【従業員の心のなか】
今ある仕事に加えて、カイゼン活動のための時間がどこにあるのか?
慣れた作業が変わるとミスを犯して責められる。慣れた作業のままでいい。
今の仕事の進め方や作り方を変えることになる。新しい事を覚えるのは大変だ。
提案をしたとしてもうまく行かなかったら自分の責任になる。
以前、提案したけど時間がたってウヤムヤになった。
何を言っても変わらない。できない理由ばかりを挙げられて変わらなかった。
カイゼンをおこなって生産性が向上しても給料が増えるわけでもないし。
生産性が向上して人手が余れば配置転換や、雇止め嘱託の更新をしてもらえない。
前の派遣先の会社ではもっと良いことしているけど、派遣社員だから関係ないし。
コンサルでは生産性について講習が有るが難しい言葉でピンとこない。
尊敬する上司から教えてもらった業務だから、これが正しいに決まっている。
前にトライしてみたがうまく行かなかった。
食品技術が判らない専門家が現場に口出しして、菌が増えたらどうするんだ?
経営者がスピーチをしている時に、従業員の曇った顔を見て思います。
人手不足、原料高騰で厳しいのに危機感がまるでない。
言われないと動かない。自発的に動いてくれない。
生産性が向上すれば賞与で還元すると言っているのに動いてくれない。
カイゼン活動の最初は動くが、気が付けば活動が停止してしまっている。
現場から出てくるカイゼンは大した内容じゃないから私の案を優先させよう。
現場の事は経験が浅いので口出しすると反発される。
コンサルがカイゼンをおこなったが契約が終われば元通りになっている。
「残念なカイゼン活動図鑑」として皆さんも経験、見たことがあるのではないしょうか?

カイゼン活動を定着させる方法
この様な事にならないようにカイゼン活動を定着させるポイントは
- トップダウンとボトムアップを使い分ける。
- カイゼンに関する報酬体系の明確化
- カイゼンの順序はムリ→ムダ→ムラ
となります。
①トップダウンとボトムアップの使い分け
私の恩師である小杉直輝先生から聞いた話です。
食品工場のカイゼン活動の契約をする時に依頼主に
「改善はトップダウンでおこなうが、実際におこなうのは担当者です。生産性が上がり自分の首を切るために、進んで改善する人はいない。生産性が上がっても、絶対に社員のクビを切らない。と約束して下さい。そして生産性が上がったら、余った余力は新しいイノベーションを起こし、必ず利益を分配すると社員に宣言してください。」とお願いされていました。
つまりカイゼンはトップダウンで始め、進捗を確認して継続し、成果が出れば貢献した人に利益を還元する。具体的な案や活動はボトムアップで進めると説いていました。
カイゼンの切り口はトップダウン型とボトムアップ型に分けられます。
トップダウン型は組織の権限を行使し、短時間に強力に進めるスタイル。
ボトムアップ型は関係者を育成し、課題を全員で考えて行動していくスタイル。
ボトムアップ型は成果が出るまで時間が掛かりますが、カイゼン活動が定着すると成果を出し続ける事が可能となります。また、現場担当者の案は数が集まり、その分、的を射ていることも多いです。
経営者はいろいろな経営や同業者他社の情報と知識が有りますが、現場の具体的なカイゼン案に良い・悪いには介入すべきでは有りません。
現場が自分で出した案を試行錯誤してうまく行かなかったときは、実行した時間がムダになったと考える事があります。
しかし、「なぜうまく行かなかったのか」という理由は人や現場に蓄積されます。現場の人は自分の出した案ですので成功させようと頑張りますし、肚落ちしてカイゼン活動を進める事ができます。
(経営者がカイゼン案を指示して担当者が頑張って成果を出しても、その手柄は経営者のもの。と思っていないでしょうか?)
経営者のトップダウンの作業は
A:カイゼン活動をスタートさせ計画的に進んでいるか確認する。
B:カイゼン活動が抵抗勢力により阻害されていれば権限を行使して排除する。
C:販売、生産部門の部分最適の対立を解消し全体最適を目指す。
D:カイゼン活動の結果、成果が出た場合に、その利益を実行者に分配する。
E:省人化された人員分で新しいイノベーションを起こす。
が主に挙げられます。
②カイゼンに対する報酬体系の明確化
経営者が「カイゼン活動をスタートさせるぞ!」と掛け声をかけても現場にはなかなか響かず、持続することが難しく感じる事が無いでしょうか?
現場担当者も同じく、「しんどいだけ」「仕事が増える」と否定的な感情を持ちます。そこで「カイゼンがうまく行けばボーナスの査定を上げるぞ」と言っても、ボーナスの金額が増加したのは、基本給が昇給して増えたのか、欠勤がなく勤務態度が良くて増えたのか不明確で十分な動機につながりにくく、加えてボーナスのないパート社員や派遣社員には恩恵が有りません。
そこで提案したいのはカイゼン活動の効果が出たら、かかわった人全員に明確な金額(控除などの手続きが大変なのでクオカードの様な賞品にする場合も有ります。)を支給するという方法です。
日本HR協会によりますと2022年の「食品などその他製造業」において改善1件当たりの経済効果は16,910円、一人あたり報奨金は3,056円となっています。これが一つの目安になるかと思います。
カイゼンの提案と、それに対する効果確認をおこない、かかわった人全員に対して不平等感の無い制度が必要になります。
定額にするのか、改善による経済効果の○%を支払うのか、コンペ製にするかは企業の考え方や、仕組みに合わせて決定すると良いと思います。
加えて、カイゼン活動の事務局や案件のリーダーの方は通常業務に加えて、◆勉強と新しい取り組みをおこなう。◆関係者とカイゼンに関わる調整をおこなう。◆マンネリ化する中でモチベーションを維持する。
…の直接的には評価されにくい作業に取り組みますので、この部分をしっかりと評価する事も大切です。
③カイゼンの順序はムリ→ムダ→ムラ
カイゼン活動においていきなりムダからカイゼン活動を始めると現場からの反発が多くて協力が得られづらくカイゼンが進むのには大きな労力がかかります。
そこでムリの解消からカイゼン活動を始める事を勧めています。ムリの解消は現場担当者にもメリットに直結し協力を得られやすいからです。
ムリのカイゼン活動をおこない、活動を定着させた後にムダのカイゼンに切り込んでいきます。ムダの見つけ方はトヨタ生産方式の「7つのムダ」が有名で
「加工(作業そのもの)のムダ」
「在庫のムダ」
「作りすぎのムダ」
「手待ちのムダ」
「動作のムダ」
「運搬のムダ」
「不良を作るムダ」
この中の「ムリな動作」と「ムダな動作」をカイゼンしていきます。
ムダのカイゼンが進むといよいよ「ムラ」のカイゼンに取り組みます。
ムラのカイゼンには販売側と製造側それぞれの部分最適から会社全体の生産性が高くなる全体最適となるカイゼンが必要となります。
そのためには、この対立を解消するトップダウンの強いリーダーシップが不可欠となります。

おわりに
いかがでしたでしょうか?これまでの生産性向上の取り組みの中で、何度も挑戦したけどダメだった。忙しい中でカイゼン活動自体が自然消滅したというケースも有ろうかと思います。そうだったとしても、また始めればよいだけです。今回の記事が皆さんの生産性向上のための参考になれば幸いです。
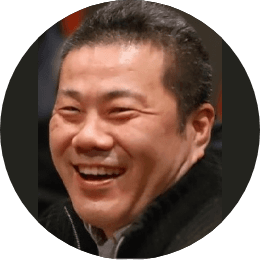
この記事を書いた人
山本 宗幸20年にわたり中規模食品会社で商品開発、事業開発、製造技術、生産性向上の業務を行ってきました。「技術で食と人を豊かにしたい」をミッションに活動しています。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


