
専門家コラム
column
給食サービス業界のDX導入事例を紹介

給食産業における顧客要求とその対応
給食産業は、顧客からの様々な要求事項を満たして成り立っていますが、大きな要求事項項目として、価格・栄養価・安全・健康・喫食者満足(施設側提供者満足)が大きな5つの要素と言えます。
経済的課題と社会情勢
これらを満たして提供するためには、価格(経済的要素)は、給食サービス業界においては大きな課題であり、今日においては学校給食受託業者の破綻が相次ぐなど、物価高騰・雇用賃金高騰・人材不足など、解決する術を各事業者の各社の皆様は血の滲む思いで模索しておられると想像するに易い社会情勢になっています。
食文化と経済的制約
食は、文化であり、それを日々摂取するものであり、その安心安全健康は、当然のものとして捉えられる一方、食事に対して費やせる費用感覚が、外食デフレ状態も悪循環を後押しして非常にシビアになっています。
そして、プライベートではスーパーでの買い物が高騰していることを身をもって体感をしている筈であろう方たちからも、給食1食の10円の値上げにも大きな抵抗をされたご経験のある事業者さんも少なくは、ないのではないでしょうか。
このような状況の中、生き残りのために、D X導入に立ち上がった給食事業者の事例を交えてご紹介をいたします。
給食事業におけるIT化の進展
給食事業では、実は古くから献立ソフトなどI T化が導入されており、献立作成・献立出力・栄養計算・調理表の出力などに役立ててきています。
今日では更に献立ソフトが発展して、衛生管理記録・発注データ出力・原価計算・栄養月日報出力など多くの機能が備わっているものも一般的になってきました。
また、クックチル調理など喫食日と調理日のタイムラグも管理できるものも普及しています。
そのほか、勤怠管理ソフトを導入している事業者さんも多いのではないでしょうか、昔はアナログに紙のタイムカードに打刻していた勤怠管理を、デジタル化して、磁気カード・I Cカードなども一般的になり、生体認証を活用して虹彩認識で目の虹彩のパターンを記憶させて、個人を特定してカメラの前を通過するだけで出退勤の管理ができるシステムなども登場しています。
これら単独のソフトウエアの導入が、一般的になってはいますが、大きなきっかけは、前途しましたように給食事業者のコストの大きな割合を占めており、管理人件費コストの軽減をねらい、導入を進める給食事業者も増えている背景があります。
これらのソフトウエア(アプリケーション)を導入しているだけでも、様々な事務作業の軽減にはつながりますが、それぞれの連携などを行うことでさらに加速的に省力化とスピード化につなげることができます。
(*アプリケーションとソフトウエアの違いは、アプリケーションは、目的に応じた機能をするために開発されたプログラムですが、ソフトウエアは広義で、アプリケーションなどを含め、パソコンそのもの自体を機能させるプログラムなど全般の総称になります。)
その結果は、専門性を高め業務に取り組むことにも直結します。
人の手を介して、創意工夫して、愛情を込め、喫食者の方に喜ばれる食事を作ることに注力ができることが目的であり、I T化やD Xが目的ではありません。あくまでも目的を叶える手段ではありますが、目的達成のための大きな下支えの手段になります。
導入成功事例
クックチル調理を行い、高齢者施設等を主に料理をチルドパックで提供している給食事業者の取り組みで、様々なソフトウエアを有効に活用し、更にソフトウエア同士や新たに開発したアプリケーションを連携をして運用を進めています。
既存のソフトウエア等
- 会計ソフト
- 勤怠管理ソフト
- 献立管理ソフト
- ラベル印刷ソフト
追加導入プログラム
- web受注アプリ(顧客注文画面・顧客向け資料提供画面)
- 既存ソフトの連携多機能アプリ
- A P Iプログラム
- ピッキングQ Rコードアプリ
- H A C C Pアプリ
それぞれの追加導入されたプログラムの概要を紹介します。
1.web受注アプリ
web受注アプリ(顧客注文画面・顧客向け資料提供画面)では、顧客からの要望に合わせた、普通食の食数・複雑なアレルギー食の食数・3種類に展開する嚥下食の食数をweb画面上で顧客の入力で受注をできるようにしました。
以前は、ファックスを中心として、それ以外にもメールや電話での、受注をしていました。 締め切りが過ぎてからの電話での変更など、事務作業者も調理者も混乱やミスが頻発していましたが、web受注アプリ上で、複雑な注文内容も明確に顧客の発注担当者より入力をしてもらうことにより、受注のミスも激減して、また自動締切設定があることにより、締切時の食数等が明確になり、現場の生産性が向上しました。
この受注情報を献立ソフトに連携させることにより、以前は様々受注方法、顧客それぞれに揃っていない受注フォームを参照しながら、個別で献立ソフトに手入力していた受注数も自動入力をされるようになり、時間短縮と受注精度向上に大いに貢献をしました。
web受注アプリ(顧客向け資料提供画面)では、I DとP A S Sを付与して、契約に合わせた、月間献立・各種献立・盛り付け指示書・栄養日報・栄養月報・請求書・お知らせ・操作マニュアル・問い合わせチャットなどを表示とダウンロードができるようにすることにより、顧客の注文に合わせた、大量の資料の印刷・整理・発送(同梱)に関わる時間を大幅に削減しました。
2.既存ソフトの連携多機能アプリ
特に顧客の個別の注文対応の中でも、アレルギーや嚥下食の対応では、代替え食の手配は、現場で余っているもの、嚥下食加工用には、概算で多めに調理したものから加工など、現場任せて運用していたために、食材原価が上がったり、また代替え食のバリエーションが狭くなりがちであったが、様々なパターンを記憶させる機能により、軽微な設定で様々な顧客要望に対応できるシステムを構築しました。
3.A P Iプログラム
A P Iとは、アプリケーション・プログラミング・インターフェイスの略です。
インターフェイス=接点同士の間を繋ぐことを指しますので、アプリケーションやプログラムを繋ぎ合わせる機能になります。
実際は、既存のパッケージソフト(献立管理ソフトなど完成形のソフトウエア)の中では、非常に幅広い用途で多くの場面でA P Iが使用されていますが、一般ユーザーの方が気がつくことはありません。
しかし、異なったソフトウエアやプログラムを利用する際には、A P Iが存在しない場合は、前途したようにC S Vで出力したデータを手作業で整えて移行したりするなど、時間と細心の注意が必要な作業を余儀なくされます。
事務作業の負担や人為的ミスの発生が頻発していましたが、自動または任意タイミングで自動連携ができるために、複雑な作業が必要なくなりました。
4.ピッキングQ Rコードアプリ
以前は、受注資料から手作業で作成されていた資料をもとに、ピッキングを行い出荷作業が行われていました。
商品の過不足、行き先のミスなど、これらの問題が発生した場合のリカバリーには、お問い合わせ受付・謝罪・状況下確認・再出荷手配・追加製造など、本来必要のない作業が重複して発生してしまっていました。
アプリを導入することにより、ミスの軽減と出荷記録の保管ができるようになりました。
人為的ミスは、ゼロにはならないものの、出荷前にQ Rコード照合のエラー検索をすることで、ミス出荷を未然に防ぐことができます。
また、出荷記録の保管があることで、顧客からの問い合わせに対して、短時間で状況説明が可能になりました。
複雑な食事を提供する給食事業者では、出荷記録がなかった時には、顧客の問い合わせ内容が全て頼りで対応が必要でしたが、出荷データを証明できることにより、顧客に対して正しい出荷状況の説明ができるようになったことで、無駄な作業が軽減されました。
5.H A C C Pアプリ
法制化された食品衛生管理システムのH A C C Pの取り組みを記録するために、人の流れと食材の流れに合わせて、記録するこののできるアプリケーションとして、既存アプリケーションをカスタマイズして導入しました。
これまでは、衛生管理は、出勤時の健康チェックや加熱時の温度管理などにとどまっていましたが、実際の調理工程に合わせた、危害要因分析を行い、アプリケーションに管理事項を記録できるようにして、エビデンス(証明)を残しています。
製造物の安全証明、記録作業の簡易化、調理作業者の意識向上に大いに貢献をしています。
今回事例として紹介した給食事業者では、1〜5を中心とした、D X導入をした結果、作業ロスによる人件費の削減や正しい厳密な調理指示による食品ロスの軽減に大きな成果を出しています。
また、これまで担当者や担当部署に任せていた作業を、システム化するにあたり作業内容を紐解くにあたり、見える化や情報共有ができてさらに社内の連携が強まりました。
まとめ
給食産業は顧客要求の価格、栄養価、安全、健康、満足度を満たす必要がありますが、経済的課題が大きいです。物価の高騰や人材不足が課題ですが、DX導入により、効率化とコスト削減を図っています。献立ソフトの進化や勤怠管理のデジタル化など、IT化が進んでおり、これらの技術を活用することで、給食事業は顧客ニーズに応えつつ、運営の効率化を実現しています。DX導入事例からは、技術活用による作業ロスの削減や食品ロスの減少など、多くの成果が得られていることが分かります。
もっと詳しく給食産業のIT化、DX化を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
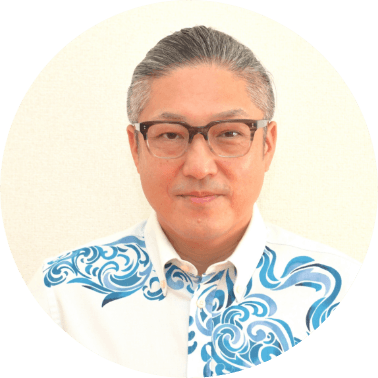
この記事を書いた人
大西 周食のプロに仕組みづくりを支援するコンサルタント業を25年営んでいる中で、今の日本に不可欠な食品事業者向けのデジタル化・D X化を推進するコンサルタント事業も5年前から取り組んでいる。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


