
専門家コラム
column
工場の建て替え・増設ができない?食品工場の改築前に調べるべきこと
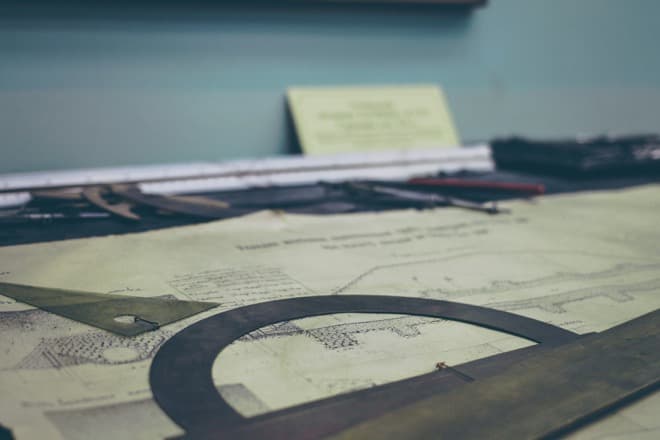
食品工場を建て替え・改築・増設したいと考えても、実は建て替えができないケースがあります。特に50年から60年ほど前に建てられた工場の場合、入念な調査を事前に行う必要があります。
本調査をしっかり行わなければ、法令上改築ができない事態が生じてしまうことも。
本記事ではその背景と、実際の実例、事前に調査すべき事項についてご紹介します。
なぜ?古い食品工場が陥る「改築や増設ができない」ケース
工場の建て替え・改築・増設を検討し、調査を進めていくと「実は建て替えができなかった。」というケースが存在します。
御社の工場がかなり古い工場の場合、または、M&Aなどによって買収した工場の場合、以下に該当していないか確認が必要です。
理由1:法令改正によって違法状態で建ってしまっている
最も多い理由として、都市計画法による開発調整区域で、工場が建てられない場所に工場が建ってしまっている事例があります。
昭和43年 (1968年)に制定された都市計画法によって「開発調整区域」という概念が作られました。
例えば、工場を建てても良い場所、住宅しか建ててはいけない場所など、地域によって建てられる建造物が規定されていることがあります。
しかしながら、本区分が制定される前に建てられた建物に関しては、本規定が適用されていません。つまり、当時の工場については現時点では法律に沿っていないまま取り残されています。
このような工場を建て替える場合は現行の法令に従う必要が出てきますので、建て替えができないケースがあります。
理由2:建ぺい率がオーバーしてしまっている
建ぺい率とは、土地の中でどれくらいの面積を建造物として良いかといった比率のことです。
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/kenpei_youseki/
一昔前までは法令に沿っていない建設が見過ごされていたこともあり、
古い工場については、建ぺい率が守れていないケースも多くあります。
しかし、もし改築を行うのであれば建ぺい率を遵守する必要があり、
建て替えるために「減築」といった大きさの縮小が必要になるケースがあります。
実際にあった食品工場の実例
ここで実際にあった事例をご紹介します。
ケース1:とある調味料メーカーの事例
とある調味料メーカーの事例として、工場の買収を行ったケースがあります。
買収を行った先の工場が古くなっており、建て直しを検討したところ、
本来は工場を立ててはいけない場所 (住宅地域) に建築がされている事例がありました。
そのため、改築が難しい状況だとわかり、工場の建て替えを行うならば、
別の場所へ新しく建てる必要が出てきました。
ケース2:とある製粉メーカーの事例
生産ラインの中にサイロを用いており、こちらが指定の建ぺい率をオーバーしている事例がありました。 工場の改築をするケースで建築屋さんに受け入れてもらえず、生産がとまってしまった事例がありました。
また、このケースの場合「減築」といって建て替えの際に建物を小さくする必要がでてきます。「生産性を上げるために改築をしたいのに、減築によって生産性を落とさないといけない」といったジレンマが生じてしまうケースもあります。
ケース3:とある洋菓子メーカーの事例
もう1つは、建ぺい率60%の地域での事例です。
広い敷地の中の端に建物を建てており、市町村の開発計画で、土地の中に道が通ることになりました。それによって、建ぺい率が60%を超えてしまうことになった会社さんがあります。
工場の改築等を行わないのであれば特に問題はありませんが、
もし今後改築や増設を検討した場合、建ぺい率がオーバーしてしまうことになります。
この場合、減築が必要になってしまいます。
事前に調査すべき項目
御社ももしかするとこのような事例に当てはまる可能性があります。
そのため、もし改築などを検討している場合は、以下の調査を事前に行う必要があります。
1. 地域区分
先述の通り、土地には行政によって定められた区分があり、まずはじめに今工場が建っている場所が開発調整区域かどうか?を確認する必要があります。
開発調整区域でなければ何を立てても問題有りませんが、開発調整区域に該当する場合は、地域によって建てられる建物が決まっています。
例えば、工業地域、準工業地域、住宅地域...と分かれています。
今立っている場所が、工場を立ててはいけない「住宅地域」ではないかどうかについて
まず確認をする必要があります。
2.最新の法令に遵守できているか
古い工場が建てられてからアップデートされている法律は、「都市開発法」だけではありません。
例えば、建築基準法や消防制や省エネ法など、工場が建てられた後に整備された法律もいくつもあります。
今回の記事のテーマである「改築」や「増設」「建て替え」には関与しませんが、
建て替えとなる場合、新たな制度に沿った工場を作る必要が出てきます。
工場建設時に遵守が必要な法律
- 都市計画法
- 各行政の事前協議または条例
- 建築基準法
- 浄化槽法
- 消防法
- 省エネ法
- 各種環境保全に関する法律
- その他立地に関連する各法律 (河川法・埋蔵文化財保護法・航空法)
建築に必要な書類が保管されているか
また以下に代表される、当時建築するにあたって役所から出された申請書などが保管されているかも確認が必要です。
古い工場の場合これらが保管されていないケースもあり、その場合は建築の専門家と相談の上、対応を検討していく必要があります。
建築時に必要な書類の例
- 開発調整区域である場合、建築許可証
- 建築確認申請原本 (計画変更前・計画変更後も含む)
- 建築完了検査済証
- 事前協議書 (福祉のまちづくり協議・法43条ただし書き許可・浄化槽申請など)
- 消防への提出書類
- 施工後からの変更・増築などの概略について
- 敷地境界のわかる図面 (測量図など)
- 既存建物の図面等の資料があるか (設計図など)
- 外部の設備機器、別棟の図面があるか
- 敷地周辺の消防水利の状況
4.建ぺい率は適切か
建ぺい率は前述の「地域区分」によって異なりますが、おおよそ60%ほどで定められている事が多いです。この建ぺい率についても過去に建てられた建造物の場合、遵守されて建てられていないケースがあります。
改築によって「減築」の必要性があるかどうか、事前に確認して検討する必要があります。
法令を守れない場合、どうすればいい?
もし調査を進めるにあたって、法令に引っかかってしまった場合はどうするべきかについて最後にお伝えします。
改築をする場合、改築の程度によっても行うべきことが異なります。
構造の変更を伴う工事の場合
構造の変更を伴う場合 =増設や建て替えが必要な場合は、現行の法規に従う必要があります。
今の時代はコンプライアンスが強く求められるため、もし法令が遵守されていない状態であれば一級建築士が図面を書いてくれなくなります。
つまり、もし開発調整区域の住宅地域に工場が建てられてしまっている場合は、
別の場所の土地を探して、そこに新設する必要が出てきます。
一から役所への確認申請 (設計をもとに建築をしても良いか確認を取る申請作業) や各種承認を取得する必要が出てきてしまいます。
また、建ぺい率の問題も確認が必要です。
建ぺい率が規定を超えてしまう場合、同じ場所での改築の場合は、「減築」が必要になります。
構造を変えない 内装のみの工事の場合
構造の変更を伴わず、内部の工事のみであればそのまま遂行することが可能です。
まとめ
食品工場は長期間にわたって活用するものであり、事業を継続するならば、何回か建て替えしていく可能性もあります。
そして、今回ご紹介したようなケースに該当すると新しい場所で建て替えて、1からやり直す必要性もでてきます。
そのため、M&Aなどで工場を買収する場合は決算書だけの数字を見るのではなく、その場所で本当に長期間ビジネスを継続できるのか?
中にある機械の耐用年数はどれくらいなのか?
そういった細部まで見るようにしてください。
また、工場の改築可否についての判断は専門家でないとわからない情報も多いです。
工場の建て替えを検討している場合は、まずは専門家に相談してみてください。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


