
専門家コラム
column
HACCPって何?どんなメリットがある?

本記事では、会社として「HACCP」の導入を検討しているけど、「そもそもHACCPとは何?」「どうして大事なの?」といった方に向けて、
HACCPの基本的な考え方をご紹介していきます。
HACCPとは?従来の衛生管理との違い
HACCPとは、「Hazard、Analysis、Critical、Control、Point」のことで、製造工程の各ポイントで危害要因を分析し、その対策を講じることで食品の安全性を向上させる考え方です。
従来の衛生管理では、「抜き取り検査」と呼ばれる”最後にでき上がった商品だけ”を検査する考え方でした。しかしこれではでき上がった商品に何らかの問題があった時、どこを改善すれば問題が解消されるのかを分析・判断することができません。
そこで導入されたのが、「HACCP」の考え方です。
HACCPでは加熱工程、製造工程、保管工程 など、商品ではなく「工程」に着目します。
各工程にいくつかの重要管理点を決めることで、トラブルが生じた際にどの工程に問題があったのかを判断できるように管理がされます。
海外では、1960年代から一般的な考え方でしたが、日本では2021年6月に義務化されました。
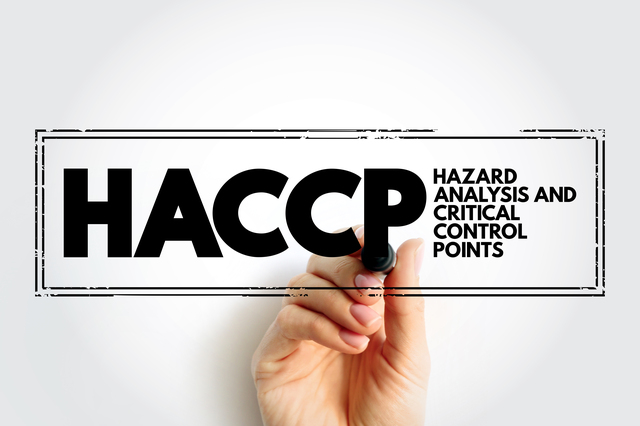
HACCP導入のメリット
コストの削減につながる
HACCPの考え方を取り入れることで
「無駄が省けた、コストが削減できた」という声が多いです。
HACCPの導入では、各工程にどういうリスクがあるか、そのリスクに対してどういう対策をしていくか、これらを1つ1つ分析しながら工程を見直していきます。
その結果、今までやってきたことでやらなくて良いことが見つかるようになります。
例えば..
- これまでは消毒のプロセスがあったたけど、最後に加熱工程があるから不要になった
- 微生物制御のプロセスをおこなっていたが、レトルト化するため不要になった
- 本来は入れなくて良い添加物が浮き彫りになった。
などです。
添加物はコストが大きいので、入れないようにすることでコストが浮きます。
本来不要だった工程を省くことで、工程がスッキリすれば、
不要だった人手が削減できるケースもあります。
2. クレームが減り、評価が上がる
HACCPで管理を始めると、異物混入や商品の不備に対する適切な再発防止策をおこなえるようになります。
従来の最終検査だと、どの工程に問題があったかわかりません。
しかし、HACCPを用いればミスが起こった工程を分析・判断することができます。
それによってクレームが減り、お客さんの評価があがることは間違いありません。
3. 従業員の意識変化
HACCPを導入すると、各製造ポイントにて各担当者が衛生管理の手順を踏むようになります。
例えば、日々管理が必要な工程を確認し、チェック表にサインをしていく程度ですが、
これが大きな意識の変化を生み、
一人一人のコンプライアンス意識が高まる結果を生みます。
また、導入に際して全部署で強力してリスクになる点を洗い出すため、
従業員の衛生に関する認識を高めることにつながります。
なぜ今?HACCPが日本で義務化された経緯
HACCPが日本で義務化するきっかけになった出来事。
それが「2020年の東京オリンピック」です。
海外では1960年代ごろから取り入れだしてすでに一般的に用いられているHACCPの考え方ですが、
日本ではこれまで全く浸透していませんでした。
その理由は、「日本人は衛生に気を使う風習があったから」です。
HACCPでの管理は、「お肉に火が通っているか確認する」「冷蔵庫の温度を管理する」など、日本では多くの企業で当たり前におこなわれている考え方です。
そのため、HACCPという明確な手順を設ける文化は浸透してきませんでした。
ただ、海外ではそうもいきません。
移民や人種が入り交じる国家では、価値観の違う人が集まるため、
手順をしっかり統一し、それを記録に残す形で管理をしなければなりません。
そんな日本も、東京オリンピックで外国人を招くことになり、世界共通の食品安全システムであるHACCP導入をせざるを得ない状況になりました。
さらに、万博の開催も控えているため、海外の不衛生な商品を入れないためにも
日本の衛生管理を国際基準まで上げることが急務になったのです。
誰がやっても、第3者が見ても、衛生管理ができるプロセスを構築する。
そういった状態が今求められているHACCPの考え方です。
「HACCPの義務化」何をすればいいのか?
「HACCP」と聞くと、難しい工程のように考えてしまうかもしれません。
ですが実際のところは
- 食品に触れる際には手袋をする
- 手洗いをする
- 加熱がしっかりされているかを確認する
などのように、日本であれば多くの企業ですでに導入されている考え方になります。
国が求めているHACCPの義務化で求めているのは、今までやってきたことを手順化・書面化することです。
私も普段クライアントさんにヒアリングすると、自然とHACCPに沿った手順ができているケースが多いです。
でも、感覚ではなくしっかりとした手順化をしないと、大きな問題が起こったときに適切な対処ができません。
普段おこなっている衛生管理を、形にすることがとても重要です。

HACCPの7原則12手順
厚生省が認める「haccpの義務化」とは、国連のCodex委員会が定める
「7原則、12手順」に基づいて作られたものを指します。
つまり、以下の7原則12手順に従った衛生管理を導入する必要があります。
→7原則12手順の記事へ
ただ、7原則12手順は中小企業、小さな飲食店にとっては
かなり難しい管理の方法です。
ですので、ここまで厳密に規格に沿ったものではなく、
HACCPの考え方だけを取り入れた簡易的な「衛生管理計画書」による
管理も許容されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\_iryou/shokuhin/haccp/index.html
HACCPって面倒。でもやったほうがいい?
HACCPの導入はたしかに大変です。
でも一度仕組みを作ってしまえば、コストダウン、納品先からのクレーム減少、従業員の意識改革、
万が一問題が生じた時のスムーズな改善など、非常に大きな恩恵が得られるのは事実です。
何も仕組みがないところから作るのが大変なだけで、いざ始めてみれば大変なことは何もありません。
何か問題が起こってからでは遅いです。
未然にトラブルを防ぐためにも、HACCPの考え方を導入することを強く推奨します。
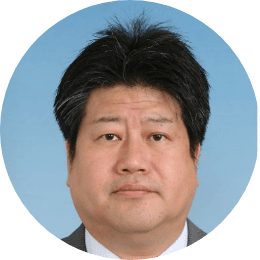
この記事を書いた人
安田 新大学で微生物学制御を学び、以後30余年、食品衛生一筋に歩んでまいりました。
コンビニの弁当工場、登録衛生検査機関、テーマパークのフードサービス部門での
品質管理・品質保証担当者として培った経験を基に活動しています。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


