
専門家コラム
column
HACCPって必要?重要性を事例を交えて解説します

HACCPとは、適切な食品衛生管理を行うための重要な考え方です。
HACCPは2021年6月に日本で義務化され、これは食品メーカーだけでなく、小規模の飲食店やベーカリーなどを含め、すべての食品に関わる企業が対象です。
本記事では、HACCPに対応予定の方、食品に対する信頼性を高めたい方に向けて、HACCPの考え方について解説します。
HACCPとこれまでの衛生管理との違い
HACCPとは、Hazard Analysis and Critical Control Point の頭文字をとった略称で、
食品における衛生管理の考え方の1つです。
HACCPが導入される前は、「最終検査」という形が用いられていました。
これは最後に商品が出来上がった段階で、「衛生に問題ないか?」「異物の混入がないか?」などを確認するプロセスです。
一方でHACCPは、「Critical Control Point:重要管理点」と呼ばれる、
製造工程の中に設けたチェックポイントを用いてリスク管理をする手法です。
具体的には「出来上がった商品」だけではなく、「調理する温度」や「保管温度」など工程ごとのリスクポイントを管理することで、問題が起こった時どこに原因があったのかを追えるようになります。
HACCPは元々 1960年代にNASAで宇宙食を作るときにアメリカで考案された考え方で、
今となっては国際レベルで多くの企業で導入されています。
日本でも2021年6月になってようやく制度化義務化がなされました。
なぜ今になって日本で導入されたのか
日本でも、HACCPのような考え方を取り入れようとしたことが何度かありました。
これまでは農林水産省が、JSFという独自の基準を推奨していましたが、
国際的にこれが受け入れられず、
結果的に国内でのHACCPの浸透を遅らせる結果になりました。
2000年に入って、リーマンショックの不景気によるコストダウンの影響で
食の安全性の問題が多発したことにより、国際的な評価を保つためにも
日本での義務化が推進されたとも考えられます。
2020年6月に食品衛生法の改正によってようやくHACCP制度化が行われ、
2021年6月に制度化義務化が決定しました。
今となっては以下のような幅広い、業界・業種の衛生管理に導入されています。
- レストラン(例:チェーンレストランや個人経営の飲食店)
- ケータリング事業(例:パーティー会場に出張、料理提供をするサービス)
- 食品輸送会社(例:倉庫における食品保管や食品の配送)
- フードトラック(例:食品の移動販売車)
- 食品メーカー(例:食品製造工場)
- 食品宅配サービス(例:弁当宅配事業)
【実例】HACCPってなぜ必要?
実際にあった事例をご紹介します。
とある食品メーカーにて髪の毛が入った、串の破片が入った、
機械の破片が入った、カビた商品を納品してしまったといった事例が多発し、品質改善の相談を受けました。
お伺いしてみるとクレームが毎日のように発生し、レポート作成・報告に、従業員のリソースが奪われている状況でした。
(毎日クレームがあると、年間300万以上の人件費の損害になります)
そこではHACCPの管理を行っておらず、
従来の最終検査がのみ行っていたため、
クレームが大量発生しても正確な原因の究明ができずにいました。
未然にトラブルを予測して危険を除去するのがHACCPの考え方です。
これが出来ていないとクレームが起きたときに、
何が原因で起こったのかを判断することができません。
これが、「最終検査」と「HACCPを取り入れた考え方」の違いです。
製造〜出荷までの工程の間で、リスクがあるポイントの管理をしておけば、納品物に問題が起こったときに、どこに原因があったかわかりますよね。
今回のケースだと、「商品への異物混入」が原因であれば、梱包以前のどこかの工程に問題があるとわかるのです。
今回の会社では、HACCPの導入により
不備食品が発生する確率が100分の1に減りました。
それによって、
- クレーム処理の対応をしていた人の手が空くようになり年間300万円以上の人件費の削減
- これまで生じていた回収・リコールのコストを削減
- クレーム前提で作成をしなくて良くなったため生産効率、利益率がアップ
といったプラスの結果をもたらすことが出来ました。
コスト削減だけでないHACCP導入のメリット
さらに、HACCPの導入には以下のような副次的なメリットもあります。
1. 営業力のアップ
クレームが大量に発生すると、営業マンのモチベーション低下を引き起こします。
既存のクライアントであれば、クレームがあっても契約が続くことがありますが、 新規のクライアントでクレームが多発したら、その矢面に立つのは営業マンです。
「クレームが減少し、食品安全性が高まる」+「HACCPを行っている」信頼性で 営業マンのストレスが減り、営業力がアップします。
2. スタッフの衛生コンプライアンスの上昇
HACCPは各管理ポイントでリスクを管理するため、スタッフの協力が不可欠です。
管理を手順化することによって社員1人1人の衛生へのコンプライアンスが上昇します。
私が提供しているコンサルティングでは、社員全員でワークショップを開いて協議を行い、担当者全員で品質を見る目を養っています。
それによって、社員の責任感や質も上がることになります。
3. 信頼性の向上
衛生管理の不備が多発すればもちろん信頼性が低下します。
食中毒などの大きな問題だと、 信頼は1回の衛生問題で大きく崩れてしまいます。
「うちみたいな小さい会社はHACCPとか関係ない」
「うちはギリギリの人数でやってるからできない」
時にはそう仰る方もいらっしゃいますが、それよりも小さい会社だからこそ、管理されていないため衛生の問題が起こりやすいのは確かです。
今はまだ、HACCPを整備していなくても契約が続いている会社もありますが、義務化されている事項なので、今後はマストになっていく管理方法です。
逆にいま衛生管理をしっかりしている会社は、信頼性が上がり、選ばれやすい状況になってきていると言えます。
【まとめ】HACCPを今すぐ取り入れるべき理由
これまでお伝えした通り、HACCPの導入には、起こるリスクを想定し、未然に防ぐ大きなメリットがあります。
さらに1つお伝えすると、将来的にHACCPを導入していないと取引を断られるケースも十分にありえます。
例えば、とある弁当屋で発生した食中毒の事例。
これはHACCP管理をしていない業者が作ったお米が原因でした。
でも世間からクレームが殺到するのは、弁当を売っていた「弁当屋さん」です。
つまり何か問題が発生したら、納品先の信頼に即座に関わります。
ですので、HACCPの導入は非常に重要なのです。
いま、品質管理の問題が起きていない会社は2種類に分かれます。
- HACCPの管理をしなくて、たまたま大きなトラブルが起こってない会社
- HACCPの管理をしていてトラブルを防止できる会社
保証されてない会社から仕入れることは今後リスクになりますし、いつ規制が厳しくなったりするかわからないので、
もしまだ整備できていない会社があれば、早めの導入を検討することをオススメします。
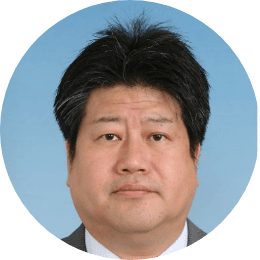
この記事を書いた人
安田 新大学で微生物学制御を学び、以後30余年、食品衛生一筋に歩んでまいりました。
コンビニの弁当工場、登録衛生検査機関、テーマパークのフードサービス部門での
品質管理・品質保証担当者として培った経験を基に活動しています。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


