
専門家コラム
column
【基礎編】DX 化とデジタル化は何が違うの?工場長が疑問に思うDX 化の進め方

DX 化が急務な理由とは
DX 化は何故おこなわれなければならないのでしょうか?それは単純にいうと1 人あたりのGDP の引き上げがどうしても必要だからです。
少子高齢化、人材不足などが深刻化しています。特に問題なのは、人材不足だというのに、給与水準が上がらない状態が続いています。
深刻なデフレ経済の中、原材料費の高騰があっても、なかなか市場価格に転嫁できない、販売価格に上乗せが出来ない事で企業の収益アップが見込めない事から、従業員の給与へ反映が出来ない状態が続いています。
そして給与水準が上がらない事で、働き手を集める事も出来ない様な状態が続いています。
そうしたデフレ経済の最下層に到達しているのです。この経済状態を打破するために
もDX 化をする事によって、企業付加価値を上げ、人材強化を図り、企業基盤を盤石にする事が重要なミッションと考えます。
日本はとっても安価な国
日本は物価が安い国とよく耳にする事があるかもしれませんが、他国と比較した場合どんな状態かご存じでしょうか?
物価指数を調べるためによく使われるのがビックマック指数というのがあります。
マクドナルドは世界中にチェーン店を持っており、国毎に若干メニューが異なるものの共通して取り扱っているのがビックマックです。
そのビックマックの価格で、物価の状態が判ると言われています。
2023 年マクドナル指数トップは、スイスで7.73 ドル(1160 円:為替レート1 ドル150 円として計算)、
2 位ノルウェイ6.92 ドル(1038 円)、3 位ウルグアイ6.86 ドル(1029 ドル)、
4位アルゼンチン5.99 ドル(899 円)、5 位ユーロ5.82 ドル(873 円)、6 位スウェーデン5.74
ドル(861 円)、7 位アメリカ5.58 ドル(837 円)、そして日本は何位だと思いますか?
実は日本は調査54 カ国中44 位3.17 ドル(476 円) ※(この指標はドル表示となっており、
為替の関係で差異が生じています。2023 年11 月現在のビッグマックの実際の日本価格は450 円で都市部230 カ所では500 円と店舗によって異なっています。)
そして、中国の3.5 ドル、韓国4.08 ドルよりも低く主要先進国の中で最下位となっています。
これが日本の現実の価格です。いかに日本の食品価格が安価なのかがよく判ります。
DX 化が必要とされる理由
国内の市場価格(販売価格)が安価だと言っても、理由も無く値上げをする事は出来ませ
ん。まずおこなう事は企業内の徹底的なコスト圧縮です。ただ勘違いをしてないで欲しいので
すが、従業員の給与を押さえ込むという事ではありません。
むしろ逆なのです。優秀な従業員を確保するためには、それなりの適正な給与を企業とし
ては、出す必要があるのです。それだと経費がかさむ、コストアップになってしまうと
工場経営者の方はジレンマにおちいる事でしょう。そこで登場するのがDX なのです。
そもそも日本の企業は、非常に生産性が低いとされています。
2020 年成長戦略会議によると2019 年の就業者あたりのGDP が米国では13.3 万ドルに対して、
日本は7.6 万ドルと先進国中最下位となっています。さらに就業時間が違うと思われがちですが、
米国では平均就業時間は1,737 時間(6.6 時間/日)に対して、日本の平均就業時間として1,702 時間(6.4 時間/日)は大きな差異はありません。
就業時間の短いドイツでも1,475 時間(5.6 時間/日)で、就業時間の長いイタリアが1,866 時間(7.1 時間/日)です
なので日本は就業時間の長さとしてはそれほど長い方ではありません。
ですが、時間あたりの生産額は44.6 ドル/時間(6690 円/時間)、これは米国の76.8 ドル/時間を筆頭に、
フランス63.4 ドル/時間、ドイツ61.4 ドル/時間、英国56.1 ドル/時間、
カナダ52.8 ドル/時間、イタリア45.7 ドル/時間と比較して最下位です。
これは日本の生産性が世界で一番低いという事を現しています。でも逆に生産性を上げる
伸び代が存在している事も同時に表しているのです。
この生産性をあげるためにDX 化技術が必要となるのです。
デジタル化なのかDX 化なのか
日本で生産性を上げるためにおこなうのが、DX 化です。
確かに、デジタル化はDX 化をする為には必要不可欠なものです。例えば、今まで手書きでおこなってきたものをWord などのアプリなどを使って作成、
もともと手作業でおこなっていた組み立て作業を自動機などを使って生産する事を一般的にはデジタル化といいます。
実はホームページを作ったり、ネットショップの運営をしたりするのもデジタル化にしか過ぎないのです。
これらはすべて実体が存在しているものなのです。
一方で、DX 化はICT(情報通信技術)を利用して、顧客の購入情報(アナリティクス)などで取得し、
分析解析をおこない、リコメンド機能を使用して、商品をオススメしたり、また購買情報を使用して、
在庫の適正化を図ったり、最適な生産予定を組んだりと、実体は伴わないのに、現実に影響を大きく及ぼしている事象の事を言います。
そのためデジタルで多くの機械や工程がすべて繋がって相互に影響を及ぼして最適化されている状態をいいます。
DX 化へのステップアップ
デジタイゼーション
ただ、DX 化の第一段階は、デジタイゼーション(デジタル化)です。既存の仕事をデジタ
ル化する事は重要なのですが、これ事態はDX 化の始まりであって、DX 化ではありませ
ん。つまり工程の自動化による省人化と呼ばれるものがこれにあたります。
デジタライゼーション
さて次のステップは、デジタライゼーションです。これはデジタル化だけじゃなくそこに
付加価値を与える事を表します。例えば生産管理が、生産予定を組むと、自社内のデジタ
ル化された、生産機械が商品を生産して、生産数を記録し、それをアウトプットして生産
管理に情報を流す。こんな事や、商品を販売する時に過去の購入情報を基にリコメンド
を出すのもこの段階になります。
デジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、デジタライゼーションと比較するとさらに進
んだ形となり、デジタル技術を活用する事で、商品やサービスの提供の制度や組織を変革
していく大きな取り組みを変えていく概念を現します。
つまり、工場でいうと顧客から注文が入ってくると、自動的に生産を計画し、その生産計
画に対して、工程の生産をおこないその結果をフィードバックする。生産データーを学習する
事で、無駄な工程を排除して、生産工程の最適化をおこないます。これによって在庫を大幅に
減らす事も可能となり、大幅なコストダウンにも繋がります。
ただ、本来の目的はコストダウンだけではありません、ネットワークを利用して、機器が接続する事で、
レスポンス力が向上し、顧客対応のスピードアップが上がる事で、顧客満足度が向上します。
例えば、受注数が突然増加したり、突発で注文が来た場合、素材、材料の調達や生産計画の調整と
納期を回答するだけで何日もかかってしまいます。これは顧客の不満足度が高くなってしまう原因のひとつです。
それがDX 化する事で、シミュレーションが簡単に出来るようになり納期の回答を即日にできるようになります。
これにより顧客満足度を向上する事が出来ます。
デジタルディスラプション
デジタルトランスフォーメーションがすすむ事で自社だけで無く、他社への影響も及ぼす事があります。
例えばAmazon がインターネット通販で本を販売する事によって、本の販売に大きな変革が起きました。
もともと書店での販売はスペースの問題があったため、書店の経営者が選択した本のみが置かれており、
すべての顧客に対して対応が出来ている訳ではありませんでした。
それがインターネット通販というプラットホームを利用する事で、誰でも欲しい
本がすぐ手に入るようになりました。この一方で既存の書店で本が売れなくなり、
どんどん閉店を余儀なくされました。
また、Apple がITune というサービスをスタートさせた事で、今まで、CD やレコードなど
を販売するという販売形態からダウンロード販売という仕組みを作り上げました。
それによって2000 年以降からCD の販売が低迷する事になりました。
そして、好調であったダウンロード販売も2015 年以降からは月次課金方式に切り替わる事によってデーター販売より
ストリーミング販売が増加する一方、YouTube で無料の音楽を聴く習慣が増えた事によってさらにCD が売れないような時代に突入しました。
音楽関係者は、CD の販売だけではだめな時代になりました。歌手はコンサートをおこなったり、
コンサートのビデオ販売、グッズ販売などファンが喜ぶような特典をつけるといったもので売上げを上げる必要が出てきたのです。
これらは一例ですが、大きな変革が発生した事例です。また共通しているのが、デジタル技術を利用する事でDX化を
おこなった事によってビジネススタイルが変化したのです。
このように、DX 化は自社のシステムだけで無く、最終的に他社にも影響を及ぼす事が可能になります。
まとめ
現在は日本の工場は従業員1 人あたりの付加価値が非常に低いのが現状です。
経営者は安価な従業員を雇っていれば何となく解決するという考え方はもう終わりです。DX 化を実践する事で、従業員ひとりあたりの付加価値を上げる事で、
厳選された優秀な従業員に高給を払いつつも、より付加価値をあげるといった体制が必要となっています。
そのためには、他社の動向をみながら始めるのでは無く、自身のデジタル改革を率先しておこなう事が重要だと考えます。
参考資料
International Monetary Fund; McDonald's Corporation; Thomson Reuters Corporation;
The Economist
企業活動におけるデジタルトランスフォーメーション の現状と課題
デジタル化と DX の違い
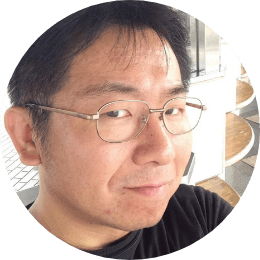
この記事を書いた人
小島 淳生産技術出身でものづくりの専門家です。工場の分析を行い工場の最適化を行います。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


