
専門家コラム
column
ISO22000認証取得の方法

はじめに
ISO 22000は、食品の安全性を確保するための国際基準です。ISO 22000の認証取得にはさまざまなメリットがありますが、認証を得るには人的資源や費用が必要となります。
この記事では、ISO 22000認証を検討している組織がよく抱える不安や疑問に焦点を当て、特に費用面や運用構築においてどのように取り組むべきかについて解説いたします。
ISO22000とは
ISO 22000は、食品の安全性を守るための取り決めが定められた国際的な基準です。
この規格に従ってみなさまの組織が運用を改善することで、以下のメリットがあります。
1.安全性をアピールできる
ホームページや名刺、営業資料、などに「ISO22000認証」と記載することで、 食品安全や品質向上への取り組みを積極的に実施している事業者であるという アピールが可能
2.二者監査の軽減・免除
取引先からの二者監査を受けている場合、規格取得によって監査を免除されたり、監査の回数や内容について軽減措置を受けられる
3.販路拡大
ISO22000の認証取得を条件に取引先を選ぶ企業もあるため、安全に関する
認証取得企業として信頼性を高めることで、販路の拡大も見込める
4.従業員の意識向上
ISO22000の認証取得によって、従業員の食品安全に関するレベルアップ。
組織単位で業務面での知識やスキルの向上も可能
5.食品安全リスクの低減
食品安全に関するリスクを減らし、クレームを減らします。
ISO 22000は企業にとって安全かつ信頼性の高い食品製造を実現するための必須条件と言えるでしょう。

ISO22000認証取得にかかる費用、期間
費用
気になる認証取得に要する費用ですが、企業の規模によって異なりますが、おおよそ初年度には50万円から100万円程度が相場です。その後、年間の維持費用は30万円から60万円程度がかかります。
認証機関によっては価格が異なりますので、まずは複数の機関に見積もりを依頼していただくと良いでしょう。安価な機関も存在しますが、その価格に見合った審査内容や認証の信頼性に注意が必要です。
期間
ISO 22000の導入支援をさせていただく場合、最低1年間の準備期間を推奨しています。ノウハウが無い状態で、すべて自社で準備を進める場合には2年の期間は見ておいた方が良いでしょう。
導入支援に際し、より短い期間(例えば半年)で認証を取得することも可能ですが、そのような認証は中身の運用が伴わず、結果としてクレームや品質不良が減らないケースが多く、お断りさせていただく事もあります。
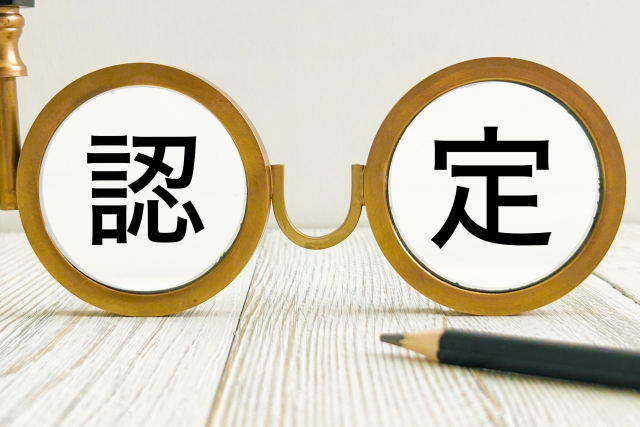
ISO22000認証取得をどのように取り組んだら良いか
次に、どのようにISO22000の認証取得に取り組んだら良いか、7段階に分けて解説していきます。
①認証の必要性を確認:
皆様の組織では、なぜISO 22000の認証が必要なのでしょうか。組織ごとに認証取得の動機は異なります。この動機は、今後構築するマネジメントシステム設計の根幹に関わる部分となります。私がコンサルティングで導入支援させていただく際には、最初にこの動機を深堀りし、確認させていただきます。
例えば以下のような動機が挙げられます:
- 取引先の要望によって取得が必要
- 営業機会・販路を増やしたい
- クレームを減らしたい
- 補助金を活用したい
- 属人化している業務を標準化していきたい など
動機が弱い状態で取り組みを進めると、後々、無用な人的負担や費用が増加してしまう傾向があります。皆様の組織内でISO 22000認証取得の動機を明らかにし、認証取得の先にある、組織としての未来・あるべき姿をしっかりと考えましょう。
②経営者を巻き込んだ活動であることを確認:
マネジメントシステムは組織全体で構築・運用される仕組みです。運用成果を上げている組織は、必ず経営者層を巻き込んだ運営ができています。ISO 22000の要求事項には、"リーダーシップ"という項目があります。トップ(経営者層)はリーダーシップを発揮し、ISOの運用に必要な投資や指示、責任の割り当て、仕組み全体が継続的に改善されることを保証しなければならないという要求です。
このような要求があるにも関わらず、トップが関与せず、一部の担当者で運用されているケースは少なくありません。例えば、品質管理部門のみが関与し、ISO審査に対応するようなケースが挙げられます。このようなケースでも認証を取得する可能性はありますが、中身が伴わない認証となり、運用成果(クレーム削減、売上拡大など)を効果的に上げることはできないでしょう。
③推進チームの結成:
ISO22000を推進・構築する中心メンバーを決めます。推進メンバーは、この後実施する文書の整備、従業員教育を含めた運用への落とし込みなどを担っていきます。そのため、組織を構成する各部門毎の代表者をメンバーとする事が理想です。下記の例のように推進に必要な責任、役割を定義します。
役職 | 責任及び役割 |
トップマネジメント | ・食品安全方針・目標の策定 ・食品安全チームリーダーの任命 ・必要な資源の提供 ・マネジメントレビュー実施 など |
食品安全チームリーダー | ・食品安全チームを管理する ・食品安全チームメンバーへの教育訓練 ・食品安全マニュアル、各種規定の作成 など |
製造部 | ・製造業務の統括 ・部門の重点実施項目の作成と実施 ・部門内教育・訓練の実施(力量の評価・把握) ・自部門の標準書の承認 など |
品質管理部 | ・製品検査 ・最終出荷責任 ・製造設備、工程変更、作業環境の承認 など |
工務部 | ・機械予防保全計画の策定・推進 ・ユーティリティ管理 など |
購買部 | ・生産計画の立案 ・資材の購入、外注加工の管理 など |
④文書システムの整備
ISO 22000の要求事項に基づき、規定・マニュアル・記録の整備が必要です。構築支援する際は、組織で既に運用している規定や記録を確認し、ISO 22000に不足している部分を特定します。その後、組織が効果的に運用できるよう、規定・マニュアルを共に検討・構築していきます。要求事項に基づく必要な文書について、以下に具体例を示します。
文書・規定 | 内容 |
HACCP文書 | HACCP7原則12手順に基づく文書・記録 フローダイアグラム、ハザード分析、CCP整理表 など |
個人衛生管理規定 | 従業員や作業者が食品製造環境での個人の衛生を確保するための規則やガイドライン 手洗い、健康確認、製造衣服、衛生教育 など |
化学薬品管理規定 | 製品の品質、安全性、法令遵守を確保するために必要な薬品導入・管理、使用に関する規定 |
設計開発規定 | 製品やプロセスの設計段階で遵守すべき基準や手順の規定 原材料・資材のサプライヤーの選定 製品やプロセスの潜在的なリスクの評価と管理 |
清掃・洗浄・殺菌規定 | 製造設備や環境を清潔かつ衛生的な状態に保つための指針や手順 適切な洗浄剤の使用、作業手順、定期的な清掃スケジュール など |
ここで紹介した文書は、要求事項に対応するために必要な文書のごく一部です。完全に文書の仕組み(システム)を構築するには、3か月から半年は見ておいた方が良いでしょう。
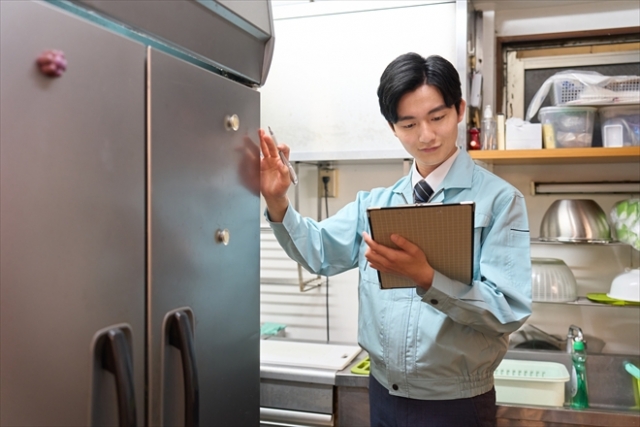
⑤トレーニングと教育
関係者に新たに構築された規定、マニュアル、記録、および運用ルールの教育訓練(トレーニング)を実施します。ISO 22000に取り組むと、多くの新たな規定や運用ルールが構築されます。すべてを一気に詰め込むことはできないため、新たなルールが策定されるたびに教育を実施していかなければなりません。
このような観点から、従業員や作業員の方に教育を実施するための時間の確保が必要です。教育を実施している間は生産活動に従事できませんので、短期的には利益率が下がる可能性があります。その点においても前述の経営層の理解が必要です。
⑥内部監査
自社で作り上げた③責任役割から⑤トレーニングと教育 までの実行段階が、意図した機能を果たしているかを自社で確認します。この確認を検証活動、内部監査と言います。内部監査を実施するためには、自社の業務の理解に加えて、ISO 22000要求事項の知識、内部監査員として求められる技能が必要となります。
コンサルティング支援をする場合には、内部監査員のためのトレーニングを実施します。この内部監査がうまく機能し、自社で問題点を見つけ、改善につなげる組織のシステム(仕組み)は強力です。認証取得を目指す場合には、運用の構築(実行段階)から内部監査(検証段階)のサイクルで問題点を見つけ、繰り返し改善を実施していくことが重要です。
最終的には外部のコンサルティングに頼らず、自社で運営できるようになることが理想です。
⑦審査機関の選定・審査
認証取得ができる見込みとなったら、いよいよ審査を受け、認証取得に取り組みます。
見積り依頼:認証機関を選定し、見積を依頼します。
認証機関を選定後、契約します。
第一段階審査:規格要求事項に即したマニュアル、手順類の策定状況が
審査されます。
第二段階審査:第一段階審査から、2か月から半年以内に実施されます。
文書に基づいたシステムの導入・運用状況が審査されます。
第二段階審査で認証取得が承認されると、3年間有効な登録証が発行されます。 以後、年に1回認証を維持するための審査を受ける必要があります。
まとめ
ISO 22000は、食品の安全性を守るための国際基準であり、組織が運用を改善することで多くのメリットが得られます。認証取得には一定の費用と期間がかかりますが、投資に見合った成果(販路拡大、クレーム削減、企業モラルの向上など)を期待できます。ぜひ認証取得に取り組んでいただき、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人
赤谷 淳一◆製パンメーカー:品質管理部門に従事しHACCPを導入
◆インターネット小売り:新規倉庫の立上げ、生産性改善業務をリード
◆ISO認証機関:審査、研修講師を担当
◆独立し、HACCP導入・コンサルティングを提供
食品製造、飼料、食品保管倉庫・配送、食品容器包装等、幅広い食品関連企業に対するコンサルティング経験・実績が強みです。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


