
専門家コラム
column
食品産業の未来を切り拓く!技術開発と新商品開発の課題解決

食品産業において、技術開発と新商品の開発は、市場の要求に応えるために不可欠な要素です。この分野での進歩は、食品の課題の解決から始まり、製造プロセスの革新によってさらなる価値を生み出します。製法、条件の最適化、設備の付加価値技術の活用により、新規プロセスや条件を開発することが、業界の成長と消費者の満足に直結しています。食品技術・プロセス開発及び改善の最前線に焦点を当て、これらの革新が如何にして食品産業の未来を切り拓いているかを探ります。
1. 食品における課題
① マーケティング戦略
「良い製品を作ったから必ず売れるはず」
「こんなに高価な原料を使っているから値段を高く設定しても売れるはず」
「高齢者の方々は、お金を持っている方々が多いから高くても買ってくれるはず」
などと言われる方が結構いらっしゃいます。
これらの言葉を発していらっしゃる会社の製品は、確かに良いものかもしれませんが、それが本当に市場に受け入れられて売れているかと言うと、必ずしもそうではありません。
これはプロダクトアウトの状態であって、マーケットでは必ずしもそうではありません。 昭和の高度成長期の時代にはそれもあったかも知れませんが、今は全く違います。
現在は消費される方々、つまり消費者がマーケットを創る時代です。つまりマーケットインです。ニーズが無いものを開発しても、またそのカテゴリでの商品が飽和であったりではニーズがありません。
新商品を購入して頂けるターゲットを、さらにペルソナを設定し、会社、製造の強みを生かし新規に製品を作り上げる製造の技術とマーケット戦略を練り上げたものが新商品、そしてこれが商品開発です。
② 「品質」の保持及び向上 品質に関しての賞味期限3分の1ルール
安全・安心な製品の提供、消費者、末端使用者の「少しでも新しいものを!」との思いから“賞味期限”や“3分の1ルール”など、品質保持に関する規制があります。
安全で安心な食品をお客様にご提供し食べて頂くという考え方から設定します。
食品劣化の3要因の生物的要因・化学的要因・物理的要因を理解し制御して、さらの食品劣化の3要素となる温度・水分・酸素をいかに制御していくかが、食品製造、開発の重要なポイントです。
③ 「味・風味・食感」の付与
美味しいと言われる食品の要素の味・風味・食感・余韻(余韻が購買意欲、つまりリピートになります)を目標とする製品にどう付与し、残し、再現し、均一に製造するかが製造技術です。
つまり②同様に食品劣化の3要素の温度・水分・酸素を制御して、維持していくことが重要だとご理解頂けますでしょうか。
④ 製造プロセス・条件の改善
食品は、同じ食品であっても個体差・不定型・品質差など、違いがあります。
それを、水分の調整、相の変化による冷凍技術、乾燥技術、さらにその温度、加工時間、圧力、さらに自然調味料(食塩、砂糖、等)により、品質を損なわずに品質を保持し、または新たな品質を確立し、保存性を向上しつつ、新商品の開発を行います。全て、品質の3要因の生物的要因・化学的要因・物理的要因によるものであり、そこを制御することで、新たな加工技術、応用技術を反映させ、新たな産物つまり新商品を生み出すことになります。
ちなみに、その個体差、不定型、品質差があるがゆえに、食品工場の完全自動化は難しい課題になります。また、完全自動化した場合に、そのネックとなる設備が故障した場合には上流、下流共にライン停止せざるを得ず不良品率、中間仕掛り廃棄、などが発生しSDGsからすると反対の方向になります。
⑤ 製造コスト改善;ムダの見える化、削減
コスト構造を、変動費(比例費)、固定費、利益に分けて考えると、変動費は、歩留り向上、エネルギーコスト削減(適正化)、他、固定費は、人件費削減(適正化)、生産設備保全、設備償却改善(設備投資額削減)など収益を向上させるために、検討する必要があります。
4Mと言われる、
原材料・製品;Material
人;Man
機械;Machine
製法;Method
を見直すことが必要です。これが食品エンジニアリングです。
つまり商品開発をすることは、そのもののアウトプット商品を市場のニーズに見合った原価で生産出来るように新規プロセス、条件及びそれを製造する生産機器も重要なファクターとなります。
2. 食品開発のマーケット課題、技術応用の解決策
① 内部環境、外部環境の強み、弱み、機会、脅威
外部環境、内部環境を鑑み、自社の強み、弱み、機会、脅威(競合他社の情報)、を要因分析し、商品開発の方向性を設定し、商品を開発します。
いくら差別化される技術、物を持っていても、市場にニーズの無いものを開発しても無駄な時間を費やすだけです。
② マーケットインとペルソナ
例えば、20歳後半から30歳前半のキャリア女性で、結婚され、子供さんがいらっしゃる。そして、毎日仕事に追われているが家族も仕事も大事、仕事帰りに駅中のショップに寄って夕飯の買い物、おつまみを購入する。月一で、ちょっと贅沢して、外食、買い物をする、というようなターゲットと言うよりペルソナです。
大きい森ではなく、その中の一本、一本の樹木の集団です。 それらは、顧客の欲求や願望を取り入れるだけでなく、それに顧客が予想しない価値を付加し驚きと感動を持つものを作ること、ストーリー性を持つことです。 最近のスーパーでは、「中食化」が進んでいます。
コロナから解放され第5類になっている影響もあり、出前、宅配、配達で、総菜系、個食化、カット野菜、健康志向、無添加などなどがキーワードとなり、新たな食のマーケットを構成しています。
食品加工技術の情報、知識、知見、スキルの習得も大切な要因です。 「差別化された付加価値のありストーリー性のある商品」です。
③ 新たな加工技術の応用
食品の課題を解決する方法として、その課題を機能ごとに解決する添加物をいく種類か適量加えて解決する方法もありますが、最近の無添加、健康指向ブームから製造方法、加工技術によりその課題を解決する方法を推奨したく思います。
ここでは加工技術、条件を加工技術、冷凍技術、乾燥技術、またはそれらの組 この技術により、他社には出来ない、ここにしかない物、他には無い物、を開発する 方向性を立てて行きたいと思います。
例えば、風味を損なわずに元の状態に戻す技術として“フリーズドライ”があります。 この技術は、お味噌汁のような液状の物を味、風味、食感を極力損なわずに流通させるもので、「急速冷凍技術」と「真空乾燥技術」を組み合わせて、新たなマーケット商品を創り出したものです。
このように、加工技術、条件により付加価値があり差別化される商品の開発が可能となります。
④ 冷凍技術は日進月歩
冷凍技術は“冷凍変性”の改善(水の液相から氷の固相への膨張による細胞の破壊によるドリップ現象)が課題解決の主体的目標になります。
いかに、水(液相)から氷(固相)に変わる最大氷温結晶生成帯をいかにして短時間で通過するか、もしくは、氷の膨張をいかにして防ぐかが、冷凍技術の永遠のテーマとなります。
⑤ 乾燥技術は日進月歩
乾燥技術は“乾燥による繊維化”の防止と“水分活性の制御”が課題解決の主体的課題になります。
さて、ここで、食品R&Dの事例を紹介しましょう。
加工食品、冷凍食品のメーカーでの事例です。
冷凍食品のマーケットにおいて、画期的な解凍加熱方法のマイクロウェーブ電子レンジの普及により食の文化が大きく変化してきました。
同時に、技術的課題としてクローズアップしてきたのが、冷凍食品の永遠の課題と言われている、冷凍品の品質の劣化(冷凍変性、冷凍焼け、解凍時のドリップ(凍結の氷結晶生成における細胞壁の破壊)、ワンフローズン・ツーフローズンの劣化)や冷凍保管中の具材の水分移行”などです。
それを解決すべく、凍結前の製品と同等の品質を保持することを目的として各メーカーが、プロセス条件、急速凍結などのエンジニアリング、添加物の調整などの開発に取り組んでいます。
例えば、現在は巷で「冷凍餃子」がヒットしています。
これは、購入されたユーザー、消費者がご家庭の焼きフライパンで焼き調理し、お店で食べる餃子と同等のものをご家庭で食べることが出来る商品として市場に認知されています。焼きによる皮のパリパリ感が美味しさのひとつですから、消費者による焼き作業による工程が必要です。これが現在は認知されています。
しかし、冷凍加工食品A社は、強みに加工食品、冷凍食品での技術的、製造的、そしてマーケットチャネルの強みがあり、それにより電子レンジ加熱加工品に重きを置き、電子レンジ調理焼き餃子を商品化開発しました。
それは、どうしても冷凍流通、冷凍加工により、電子レンジで加熱しても、皮のパリパリ感を再現することは出来ません。
専用の設備も投資し、生産し、先行し販売して行きましたが、やはり焼き餃子は皮のパリパリ感が重要な美味しさのファクターですから、発売当初は話題になりましたが、工程、条件、投資により製造原価も市場のニーズとはほど遠いものとなり、マーケットは、そう長くは続きませんでした。
それは、マーケティング解析の不足、味、風味、食感の美味しさの要素の認識の甘さだったと思います。 ちなみに、焼売(しゅうまい)は、皮のパリパリ感は要求されない(蒸し物であることから)ため、焼売の電子レンジ加熱調理製品は市場に受け入れられている。
3.まとめ
このように、まず目標とする加工品をどのように開発して行くのか、マーケットインでありニーズはあるか、消費者はその商品に何を求めているのか、自社の強みを生かしつつ、弱みを補強し、考えられる素材の特性を生かして、加工技術により新たな付加価値のある商品を作り出して行くことを目標に取り組んで行くこと、それがこれからの食品の技術開発、商品開発の進むべき方向性と考えます。
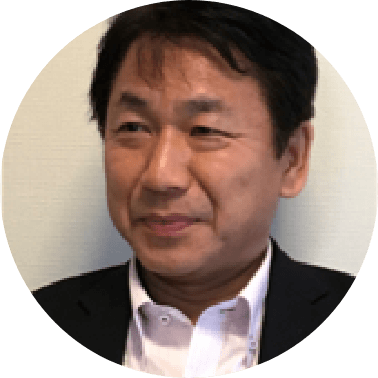
この記事を書いた人
久壽米木 正一食品全般のR&D、食品工場基本設計建設、食品工場生産性改善・原価低減化の、経験、実績、スキルから、食品事業基盤、ソフト面、ハード面の構築にお役立ち致します。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


