
専門家コラム
column
IT投資と経営戦略の関係性について

I T投資は経営戦略に基づいて実行されるべきものであり、その投資効果は経営戦略との関係により分類することができます。
I T投資と経営戦略の関係性を分類して、一つの目的、または複合的な目的を明確にして効果を予測することで、計画的な投資と効果測定ができます。
多大な費用と準備をかけるI Tシステムの投資対効果をいかに向上させるかが注目されるようになっていますが、これを評価するために、I Tシステムの構築前に狙いに合致した定量的な指標を洗い出し、運用開始後にその指標を測定する手法を取りたいものです。
そのためには事前の分類や検証がなされていない状況において構築されたI Tシステムでは、効果を測定するのは困難なために、事前にどのような情報をどのように整理すべきかをご確認いただきたくご提案をします。
投資分類を3つに分けて考えていきましょう。
1、 戦略実現を直接目的とするもの
2、 間接的に戦略を実現するもの
3、 個別に対応するもの
1、戦略実現を直接目的とするもの
①プロセス改良型
ビジネスプロセスのパフォーマンス向上を目的とした投資
例)受注を自動受注システムにすることにより、受注集計作業を軽減します。
人の手を介して、受注を行うことでのミスやタイムロスも軽減できる上、集計データを瞬時に共有することも可能になります。
ファックスや電話でのやりとりで、受信ミスや重複受信によるミス受注や、電話でのやりとりでの聞き間違いなども防ぐことができます。
②顧客価値増大型
顧客関係の強化により顧客増大、市場拡大を目指した投資
例)商品説明資料等を常時webサイト上で簡単に検索できて閲覧・ダウンロードできるようにします。
欲しい情報をすぐに手軽に自由に入手できることは、誰もが望むことです。
問い合わせる、解答を待つなどの煩わしい時間を大幅に削減することができます。
③製品開発力強化型
製品・サービス開発強化のための投資。
例)顧客からの意見やアイデア・また顧客のシステムの活用動向を分析・収集して、新しいサービス・新しい顧客開拓に役立てました。
特定のサービスの利用時間が著しく長くやり直しや訂正が多い場合、サービス自体がわかりにくいのか、またはI Tシステムの表現を改善することで解決できるのか、など具体的な顧客動向に合わせた潜在的不便を解決することも可能です。
④ビジネス創出型
新たなビジネスを創出する投資。
例)ITシステム利用顧客の声から、新たなビジネス創出を模索。
新たなビジネス創出は、競合他社にはないサービスを提供することにも繋がり、価格競争から脱却するための近道にもなります。
同じようなサービスであっても一味違ったサービスを顧客は要望しているものです。
2、間接的に戦略を実現するもの
①組織力強化型
戦略・財務・人的資源管理など組織資本、人的資本への投資。
例)人事評価制度K P I(「重要業績評価指標」や「重要達成度指標」)の導入。
人事評価のデータ処理は膨大で煩雑な業務になるため、そのためのコストや精度を考えると、頭を抱える問題の一つではないでしょうか。
これらを自社やアウトソーシングで仕組み化することで、迅速かつ客観的な評価をするための参考データをまとめることが可能です。
②I Tインフラ強化型
アプリケーションやビジネスパフォーマンス向上への投資
例)顧客情報やクレーム・事故報告書、トラブルシューティングなどのwebアプリケーションでの情報共有プラットホームの構築。
マニュアルブックに説明不足点、落丁、未更新、複数資料の混在など、常時更新や同時共有が難しかった現場で、大いにシステム化が役立ちました。
3、個別に対応するもの
①効率向上型
業務コスト削減、販売管理費削減などにより効率向上のための投資。
例)販路動線をG P Sで管理して効率的な配送ルートや配送指示をアプリケーションで分析・指示。
配送ルート構築時間が大幅に短縮できた上に、配送ロスが削減できたために、配送コースを減らすことが実現でき、適正な指示により配送できるために、配送スタッフのストレスも軽減しました。
②情報提供型(対顧客)
顧客接点を強化、付加価値の高い情報提供を目的とした投資。
例)会員サイト・会員ページからの双方向型情報提供。顧客の声やチャットQ&A。
顧客の声に迅速に対応や対話ができることで、顧客とのコミニュケーションを図ることができた、これらの活動を元に、Q&Aやとラブルシューティングのページに反映させて、顧客要望に応えることができるようになりました。
③情報共有型
社内及び関係者で情報共有、ナレッジ共有を目的とした投資。
例)技術情報のデータや動画を関係者向けのアプリでデータ管理して公開。
ベテランのノウハウを、データベース化することで、自他社のスタッフでのサービス迅速な対応が可能になりました。
④リスク対応型
リスク・セキュリティー対策、コンプライアンスのための投資。
例)コンプライアンス遵守・内部統制のための、部署設定、ルール作成、周知、相談窓口設置、内部監査システム、さらには、人事評価のためのツールを構築。
法令遵守の周知や相談窓口の設置など、これまで必要と思いながらも進んでいなかったことが、webアプリケーションで共有や窓口を作ることで、社員が手軽にアクセスすることができることが実現しました。
⑤必須対応型
法制度改正や顧客からの必須要求事項に対応するための投資。
例)顧客からの必須要求事項など、最新情報をアプリケーションで管理し、アップデートされた際には、全員閲覧・既読記録が取れるようにしました。
要求事項が複雑で、変更が生じる顧客に関して、専任担当者が膨大な時間と労力を要して対応してきたが、webアプリケーションで管理できるようになり、多くの社員で対応することが可能になり全体的な業務分担ができるようになりました。
これら上記した、それぞれ(またはそれ以外のものも含め)の投資分類を、設定することで投資計画が策定出来る根拠ができます。
投資する分類ごとに現状のコストや利益も明確化しておきます。
そして、運用が開始〜完了された時には、R O I(投資利益率)評価をします。*R O Iとは、Retuern On Investmentの略
これは、今回はI Tシステムを導入をするために、事業活動の成功度合いを検証するために非常に有効な手法になります。
自社内や関係事業者との業務フローの複雑化や顧客のニーズ多様化が顕著な今日において、客観的かつ定量的な評価をすることを目的とします。
R O Iを用いると、規模の異なる部署間で有っても比較することが可能になります。
R O Iの計算式は、利益金額÷投資金額、に100を乗じて%で表します。
算出したR O Iは当然数値が大きれば大きいほど収益性に富んだ投資と判断できます。
0%が損益の分岐点になりますが、I Tシステム構築時には、R O Iが0%であっても戦略的に人件費をI Tシステムに置き換えて考えた場合、継続的に考えると利益が将来的に大きく伸ばせる可能性もあります。
そのために、評価する期間(効果の出る期間)である完了時期をあらかじめ見込んで計画する必要があります。
R O Iのメリットは、前記した通り、異なる事業の費用対効果を評価できることです。部門毎での成果の正しい評価ができることで人事評価には大いに役立つのです。
このように、I Tシステムを導入する際に、単に利益が出た出ないを結果論として検証するのではなく、事前に経営戦略的にI T投資を行うことで、必要に応じた思い切った投資準備や資金調達ができるのです。
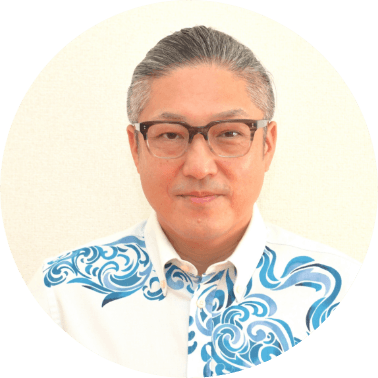
この記事を書いた人
大西 周食のプロに仕組みづくりを支援するコンサルタント業を25年営んでいる中で、今の日本に不可欠な食品事業者向けのデジタル化・D X化を推進するコンサルタント事業も5年前から取り組んでいる。
今週のピックアップ記事
Pick Articles

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販路開拓
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

海外進出
2024-08-01
荒島 由也
スター・コンサルティング・ジャパン・STAR KITCHEN 代表

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役

販売促進
2024-08-01
竹内 涼太
バディコンサルティング株式会社/たけうち中小企業診断士事務所 代表取締役


